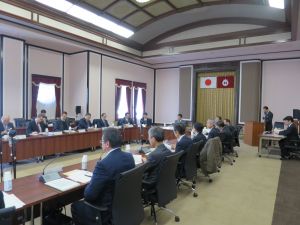○設立趣旨
平成18年2月に地域内の企業、南相馬市、原町商工会議所などの連携により、機械金属加工産業の発展と技術力向上、新産業創出を目指し「南相馬機械工業振興協議会」が設立され、その後、平成23年12月に東日本大震災以降の新たな経済成長と雇用創出を実現するため、官民一体となってロボット関連産業の創出を目指し「南相馬ロボット産業協議会」(旧)が発足しました。
このふたつの協議会は、互いに協力して活動を行っておりましたが、より広い分野の技術を有した一つの技術集団として、会員相互にさらなる知識や技術力の向上を図るとともに、互いの技術を活かすことで各々の分野におけるビジネスチャンスを創出し、地域全体の産業の発展をより強力に推進するため、平成28年6月に新生「南相馬ロボット産業協議会」として統合されました。
一方、ロボット関連の技術は、災害対応のみならず他の多くの分野に於いても広く必要とされる重要なものでありますが、技術発展には、機械・金属、エレクトロニクス、IT・通信、デバイス、その他関連産業における、個々の高度で実践的な技術開発と、それらを融合させる必要があることから、産業を支える「ものづくり」に不可欠な要素技術(精密微細加工や特殊素材合成加工など)の、現場レベルでの迅速かつ高度な「擦り合わせ」を行うことが出来る環境を整える必要があるとされております。
本協議会は、主として相双地域に集中した多岐にわたる専門分野の企業を会員にもち、加えて学術機関・行政・経済界との連携により、まさにロボット産業発展の期待に応える環境を整え、地域産業の発展に寄与するため設立いたしました。
「ロボット関連組織・団体・企業」 ・ 「大学・産学官連携組織」の検索結果
南相馬ロボット産業協議会
福島県廃炉・除染ロボット技術研究
福島県廃炉・除染ロボット技術研究会では、廃炉・除染分野への事業参入を検討する県内企業を支援するため、国や関係機関、大学等と連携し、技術セミナーや先進地調査、企業間マッチング等を実施しています。
とやまロボット技術研究会
県内企業が持つものづくり技術を活かし、ロボット産業を次世代の成長産業の柱として育成していくため、産学官連携によるロボット技術開発の推進並びにロボット産業活性化を目的に『とやまロボット技術研究会』を運営しています。
早稲田大学 グリーン・コンピューティング・システム研究機構
早稲田大学では、本学のグリーンCITに関する研究開発を積極的に推し進め、低炭素社会の貢献、高度CIT機器の高付加価値化による産業競争力の強化に貢献するため、グリーン・コンピューティング・システム研究機構を設置しました。本機構は国家プロジェクトをはじめ、産官学による産学連携研究に積極的に参画する事で、最先端技術の社会への還元を図ります。
グリーン・コンピューティング・システム研究機構
機構長 松島 裕一
気候変動問題は地球規模の重要課題となっており、環境に配慮した持続可能な低炭素社会の実現は国家目標ともなっております。これに向けたグリーンイノベーションの推進は、気候変動問題の解決を図るとともに、我が国の「新成長戦略」におけるエンジン役を担う重点テーマと位置づけられております。
本学においてもグリーンイノベーション推進に必要となる「情報通信技術活用による低炭素化」に貢献する研究として、超低消費電力プロセッサ、クラウド・システム、スマートグリッド等、様々な次世代ICT技術に関わる研究を、理工学術院、IT研究機構、国際情報通信研究センター、情報生産システム研究センター等を中心として、これまで積極的に進めてまいりました。また、産業界とも積極的に交流し、NEDOマッチングファンド事業や共同研究、委託研究等により、研究開発された技術を社会に還元すべく活動してまいりました。
本学ではこれらのグリーンICT技術の研究開発を更に強力に推進するため、経済産業省「産業技術研究開発施設整備事業」 による支援を受け、新たな産学連携研究の拠点として「グリーン・コンピューティング・システム研究開発センター」を平成23年4月に竣工し、本拠点を中心に研究を推進する組織として「グリーン・コンピューティング・システム研究機構」を設立いたしました。
本研究機構では超低消費電力で高性能なメニーコアプロセッサを中核としたグリーンICT技術の研究開発を産学連携によって推進していきます。この目標を達成するため、アーキテクチャ、チップ設計技術、コンパイラ技術、ソフトウェア技術などの要素技術、さらにはこのプロセッサを利用したサーバ・情報家電・ロボット・自動車等への応用展開など、広範囲な研究課題に挑戦してまいります。また、学内の組織やキャンパスをまたがる研究プロジェクト、産官学連携による共同研究、国内外の第一線級研究者の招聘、学術交流等も積極的に行い、最先端の研究拠点として活動してまいりますので、ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ICT・ロボット工学拠点(早稲田大学 スーパーグローバル大学創成支援(SGU) Waseda Ocean構想)
最新の自動車、航空機、精密機械、ロボット、家庭電気製品は、機械工学、コンピュータサイエンス、通信技術が統合(integration)されたシステムです。それらのシステムに人がつながり、新しい知的社会(intelligent society)が生まれつつあります。最近流行のIoTもその中の一部といえます。このような時代に大学の工学系に求められることは、この社会の構築を進めていく中で、イノベーションを創出できる人材を育てることです。しかし、近年の急速な専門分野の拡大は、学生諸君の勉学の負荷を増大させ、学際的な知識獲得・経験の機会を狭めています。また、実用化を強く指向した開発計画が企業等には歓迎されるため、大学本来が持つべき長期的なビジョンを見据えた研究の展開が弱くなっています。このような中で、視野の広い人材育成が大学院の教育システムに期待されています。この教育で重視されるべきは、国際化であり、学際化であり、そして新研究分野を開拓するチャレンジ精神の高揚です。
早稲田大学の機械系・情報系のチームは、2013年、文部科学省のプログラムである博士課程教育リーディングプログラムに採択され、「実体情報学博士プログラム」を立ち上げました。これは5年一貫性の大学院教育プログラムであり、Embodiment Mechanism、Computer Science、Networking Technologyの3分野を対象に、それらの発展の歴史と技術的関連性を理解し、それらを融合した新しいもの作りによるイノベーションが提案できる力を持った学生を育成するプログラムです.異なる学部・学科を卒業した学生諸君が一つの場所:プログラムの専用スペースである「工房」に集い、研究知識を共有し、刺激をし合い、そして留学し、毎年QEによる評価を受けるのです。
SGUのICT・ロボット工学拠点は、この実体情報学博士プログラムをベースに構成されています。本拠点では、海外教員との共同研究推進、有力研究機関への留学だけでなく、海外の著名アドバイザを含めた複数研究指導体制の構築を進めており、リーディングプログラムに設置した科目群による教育との相乗効果により、学生諸君のモチベーション向上、先見力の会得、そして研究力強化を目指しています。
早稲田大学では、研究室、学科、専攻の壁を越えて積極的に連携しようとする校風があります。その中で機械系と情報系の連携によって早稲田の研究力はますます強くなります。早稲田大学が掲げるVision150達成へ向けて、ICT・ロボット工学拠点は「連携」をキーワードに掲げて、その先頭を走っていきます。
早稲田大学 重点領域研究機構 アクティヴ・エイジング研究所
【研究テーマ】
超高齢社会の到来を見据えたアクティヴ・エイジングを支える先端理工学とスポーツ科学の融合研究
【研究概要】
本重点領域「超高齢社会におけるパラダイムシフト」の研究においては、スポーツ科学、ロボット工学、生命科学の3研究グループのこれまでの研究成果を踏まえて、超高齢社会の到来を見据えた先端理工学とスポーツ科学の融合研究を発展させる。「高齢化が進んだとしても、人間として健康で楽しく生活する機能が保持される」社会の構築が不可欠であり、それを支える研究は喫緊の重要課題であるとの認識に至り、“アクティヴ・エイジングを支える先端理工学とスポーツ科学の融合研究”を提案することとした。
Sグループが中心となる研究では、早稲田大学校友を対象としたプロジェクト“WASEDA’s Health Study”を立ち上げ推進する。中高年男女の健康・体力に及ぼすライフスタイルの影響を遺伝子多型、若年期、成人期におけるスポーツ経験と、現在の健康リスク、体力指標(心肺体力、筋力など)と関連させ横断的に明らかにする。また、Rグループと連携して新規運動機器を開発し、それを用いて高齢者に対する健康効果を評価する。さらに、Tグループによって開発された測定系を人に応用した研究へと発展させる。
Rグループが中心となる研究では、ロボット工学、生命科学、スポーツ科学のこれまでの知見を統合し、「アクティヴ・シニアのためのセルフメディケーション」を支援するための基礎理論の確立とそれを支援する機器の開発を一貫して実施する。具体的には、ロボット技術を用いたトレーニング機器開発、スポーツ科学に基づいた高齢者のためのトレーニング開発、 食や生活習慣の健康・トレーニングへの影響の科学的な解明を実施する。
Tグループが中心となる研究では、Rグループと共同で機能性蛍光プローブや導電性高分子を用いたナノシートを開発し、生体情報をモニターするシステムを構築する。また、機能性ナノシートの評価試験はTWInsではin vitro, in vivoまでを行い、Sグループと共同して人を対象とした研究にて実証する。また、時間軸の健康科学や生活習慣病・がん予防の生命科学による基礎的、応用的研究から高齢者の健康効果を実証する。
スーパーグローバル大学創成支援(SGU)「Waseda Ocean構想」 ICT・ロボット工学拠点
最新の自動車、航空機、精密機械、ロボット、家庭電気製品は、機械工学、コンピュータサイエンス、通信技術が統合(integration)されたシステムです。それらのシステムに人がつながり、新しい知的社会(intelligent society)が生まれつつあります。最近流行のIoTもその中の一部といえます。このような時代に大学の工学系に求められることは、この社会の構築を進めていく中で、イノベーションを創出できる人材を育てることです。しかし、近年の急速な専門分野の拡大は、学生諸君の勉学の負荷を増大させ、学際的な知識獲得・経験の機会を狭めています。また、実用化を強く指向した開発計画が企業等には歓迎されるため、大学本来が持つべき長期的なビジョンを見据えた研究の展開が弱くなっています。このような中で、視野の広い人材育成が大学院の教育システムに期待されています。この教育で重視されるべきは、国際化であり、学際化であり、そして新研究分野を開拓するチャレンジ精神の高揚です。
早稲田大学の機械系・情報系のチームは、2013年、文部科学省のプログラムである博士課程教育リーディングプログラムに採択され、「実体情報学博士プログラム」を立ち上げました。これは5年一貫性の大学院教育プログラムであり、Embodiment Mechanism、Computer Science、Networking Technologyの3分野を対象に、それらの発展の歴史と技術的関連性を理解し、それらを融合した新しいもの作りによるイノベーションが提案できる力を持った学生を育成するプログラムです.異なる学部・学科を卒業した学生諸君が一つの場所:プログラムの専用スペースである「工房」に集い、研究知識を共有し、刺激をし合い、そして留学し、毎年QEによる評価を受けるのです。
SGUのICT・ロボット工学拠点は、この実体情報学博士プログラムをベースに構成されています。本拠点では、海外教員との共同研究推進、有力研究機関への留学だけでなく、海外の著名アドバイザを含めた複数研究指導体制の構築を進めており、リーディングプログラムに設置した科目群による教育との相乗効果により、学生諸君のモチベーション向上、先見力の会得、そして研究力強化を目指しています。
早稲田大学では、研究室、学科、専攻の壁を越えて積極的に連携しようとする校風があります。その中で機械系と情報系の連携によって早稲田の研究力はますます強くなります。早稲田大学が掲げるVision150達成へ向けて、ICT・ロボット工学拠点は「連携」をキーワードに掲げて、その先頭を走っていきます。
最先端研究開発支援プログラム 最先端サイバニクス研究拠点
【最先端サイバニクス研究拠点の概要】
1985年に科学万博が開催された、日本を代表する研究学園都市・つくば市。
科学技術と自然環境が共存する、世界有数の知の集積地であるつくば市には、日本における国立研究機関の約半分と、民間の研究所あわせて300機関が存在しています。さらに2011年3月に日本初の「モビリティロボット特区」として認定され、6月から公道歩行実験が開始されています。
この都市の中核的教育研究機関として設立された 筑波大学 の中に、当コアセンターは設けられました。
【本拠点が主導する連携体制】
本プロジェクトは本学内に設立されているILC(産学官リエゾン共同研究センター)・CREILセンター(次世代医療研究開発・教育統合センター)・サイバニクス研究棟(サイバニクス領域)・イノベーション棟(医学系)にある拠点を初めとし、大阪大学 大学院医学系、大阪大学 大学院機械工学系、民間企業であるCYBERDYNE 株式会社と密に連携を取り、世界を牽引する最先端の人支援技術研究を推進しています。
地域イノベーション戦略推進地域「いわて環境と人にやさしい次世代モビリティ開発拠点」
産学官金連携によって、自動車の大きな部分を占める金属・樹脂の塑性加工産業を強化・拡大。 また、大震災の被災地として防災への大きなニーズや、高齢化率の進む地域として高齢化のニーズなどをICT商品化し、 震災復興に貢献し、この地をイノベーティブな次世代モビリティーの開発拠点にしていきます。 自動車部品が世界的規模でモジュール化されていく国際競争の時代においても、競争力のある地域をめざします。
グローバルロボットアカデミア研究所
本研究所では、現在早稲田大学で研究されている最先端医療・福祉技術を実用化段階に移行させることを目的としています。その主要技術として、
①低侵襲かつ高精度な手術支援ロボット
②救急救命支援ロボット
③高齢者や障害者を対象とした日常生活動作支援ロボット
④ロボット技術を応用した歩行トレーニングシステム
⑤医療技術を定量化することが可能な医療トレーニングシステム
の5つの柱があります。
本研究は前項で挙げたこれらの最先端技術を利用することにより、日本の医療・福祉レベルを大きく革新させることが可能となります。特に高齢者・患者の病気や怪我、障害などからの回復を速めるという課題をロボット技術を用いて解決することを目指しており。これらの研究技術が実用化されることにより、全ての国民のQOLを向上させるだけでなく、深刻な問題になっている国の医療費の大幅な削減にもつながります。
さらに、日本各地の医療・介護施設はもちろん、アジア諸国の広大な市場への医療・福祉システム導入を見据えており、日本の新たな輸出産業を構築する基盤になることが期待されます。
東京大学フューチャーセンター推進機構
〇取組内容
1.背景
グローバル化が急速に進展する世界では、環境・エネルギー・自然災害・感染症への対応や健康長寿社会・安心安全な社会の構築など、我が国だけでなく世界全体が直面している課題が輩出しております。このような状況下、従来の産学官連携では、大学発の技術・研究を大企業へ移転する形でしたが、研究と事業化を隔てる、いわゆる「死の谷」もありなかなか成果が出にくいモデルでした。これを克服するため、この間に市民による社会実験を入れ、市民の細かな要望に対して地元の中小企業が応えつつ、大企業・大学へとつなげ、新技術の事業化・全国・海外展開を図る「市民・中小企業が主体となる社会実験体制」という新しいモデルを構築し、諸課題の解決を目指します。
2.役割
そのフィールドを提供するのが東京大学フューチャーセンター推進機構の役割であり、それが東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライトです。その際、1.市民参加の社会実験で新技術が社会に受け入れられるか否か(社会受容性)を検証すること、数多ある既存の社会実験を整理統合し、社会実験のために必要な共通基盤を構築し、集中的に社会実験を実施することで効果・効率化を促進し相乗効果を創出し、新たなビジネスモデルを創造すること、が重要なポイントです。東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライトは、駅前という立地環境を活かし、周辺施設との協働を通じた都市環境の魅力向上に寄与するとともに、オープンイノベーションの拠点にふさわしい機能・空間の構築を推進します。
3.社会実験に必要なメリット
では何故、社会実験を柏市で行うのでしょうか。柏市はスマートシティとしての強みがあり、具体的には1.エネルギー面で電力特区に認定されていること、2.交通面でITS(高度道路交通システム)指定地域であること、3.東大等の研究機関が存在していること、4.行政・地元企業・市民・大企業の協力体制が整備されていること(東大と柏市は包括協力協定を締結、東大は柏商工会議所(中小企業支援組織)の正会員として加入、産学官連携本部(大企業との協力組織)分室と市民との窓口であるUDCKを東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト内に設置し連携)、5.東葛テクノプラザ・東大柏ベンチャープラザ等のインキュベーション施設の存在、等々で社会実験実施のための多くのメリット・好条件が備わっております。
4.活動
ここでの具体的な活動としては以下のようなものを考えております。
1.社会実験のための共通基盤の構築
・人モノサービスの稼働状態データベースの構築、人モノサービスのマッチングアルゴリズムの構築、法規制・個人情報・特区・損害賠償など共通課題の解決等
2.既に柏地区において実践し成果を挙げてきたフィールド型研究の支援機能の拡充
・スマートシティ、オンデマンドバス、地域防災システム、新交通システム等
〇設立日
平成21年3月10日
知能ロボット学研究室(石黒研究室)
石黒研究室では,未来の人間社会を支える知的システムの実現を目指し,センサ工学,ロボット工学,人工知能,認知科学を基礎として,知覚情報基盤・知能ロボット情報基盤の研究開発、そしてこれらに基づき、人間と豊かにかかわる人間型ロボットを創成する研究に取り組んでいます。
知覚情報基盤とは,多種のセンサからなるセンサネットワークを用いて,そこで活動する人間やロボットの知覚能力を補い,その活動を支援する情報基盤です.知能ロボット情報基盤とは,人間と直接相互作用することを通じ,ロボットの持つ多様なモダリティや存在感を活かした情報交換を行う情報基盤です.
人間と豊かにかかわる人間型ロボットの開発は,「人間とは何か」という基本問題と常に密接な関係を持ちます。また街角や病院などの実社会の中に実験フィールドを構築し,人と関わるロボットの社会実験に積極的に取り組んでいます.ここで研究成果を実社会で検証するとともに,知的システムを応用した近未来の
人間社会のあるべき姿を常に模索し続けながら研究を進めています.
社会ロボット具現化センター(九州工業大学)
九州工業大学 社会ロボット具現化センターは、モノづくりの基本である工学、応用工学であるロボティクスを通じた研究成果をもとに、新たな可能性を社会に提示し、研究成果の具現化およびロボット市場の開拓を目指します。
新学術領域研究「分子ロボティクス」
◆領域の概要◆
従来のものづくりの方法論は、すべて材料となる物質の塊を外部から与えた情報に従って加工することで望みの形状を得るトップダウンのアプローチによっている。最近、これとは全く逆の方法論、つまり、物質を構成する分子そのものの性質をプログラムすることにより、その物質自身が望みのものに「なる」ボトムアップのアプローチが注目を集めている。分子そのものを設計し、分子の自己集合によって、原子分解能をもつ人工物を作り上げるこの方法論の出現は、ものづくりの歴史的転換点となることは間違いない。これにより、あらゆる人工物が分子レベルの精度を持つようになれば、生体機能を人工的に再構成できるだけでなく、分子レベルの自己修復、自己改変といったことが可能となり、医療、食料、エネルギーをはじめ、さまざまな分野への波及効果は計り知れないものとなるだろう。技術立国のほか生き残るすべのない我が国としては、今まさに起こりつつあるこのパラダイムシフトを先取りしていくことが必要不可欠であり、そのための新しい学術領域の確立、またそのための人材育成が急務となっている。
本学術領域は、個別の材料やデバイスを「いかにシステムとして組み上げるか」に重点を置いて、人工的な分子システムを構築する方法論の創成を目指す新しい学術領域である。我が国の化学は世界的に見ても極めて高い水準にあり、分子システムのハードウェアとしては、すでに利用可能な要素技術が数多く存在している。しかし化学者だけでは、これらをシステムとして組み上げ、ネットワークとして機能させるためのソフトウェアの開発は困難である。そこで、ロボット工学の方法論を導入してこれらをシステム化し、従来の方法論では達成しえない「プログラム可能な人工分子システム」の実現をねらうのが本学術領域である。人工分子システムの構築は、学術的に極めて重要な研究対象であると同時に、医療、環境、食糧等、我々が直面している諸問題を解決するためのキーテクノロジーになりうるものである。
〇計画研究A01 感覚班「拡散ナノ構造を活用した多元分子情報変換デバイスの創成」
分子ロボットに「感覚」を持たせるため、一分子レベルでの「検出」、「増幅」、「変換」機能をもつ分子デバイスを開発する。DNA オリガミや RNA ナノ構造を用いることで、一定のノイズ存在下でセンシング対象となる複数の分子を多元的に検出し、B01 知能班の開発する情報処理システムへの入力情報を提供する。また、C01 アメーバ班の開発するモデル分子ロボットを対象として、リポソーム膜面上へのセンシングデバイス埋め込み技術を開発するとともに、分子モータ群やゲルアクチュエータを駆動するため、十分な濃度で任意の核酸配列を出力する技術を開発する。
〇計画研究B01 知能班「知能分子ロボット実現に向けた化学反応回路の設計と構築」
分子ロボットの「知能中枢」となる、核酸反応をベースとした情報処理システムを構築する。そのため、高速かつ安定に動作する基本演算素子を開発するとともに、過去の状態を記憶するメモリー素子と、現在の入力情報と記憶に基づいて次の状態を決定する計算機構(状態遷移機械)を実現する。
〇計画研究C01 アメーバ班「アメーバ型分子ロボット実現のための要素技術開発とその統合」
単分子型分子ロボットの限界を乗り越えるため、サブミクロンサイズのコンポーネントを人工的に合成し、その中に情報処理や運動のための分子デバイス群を統合することで、反応速度論に基づく決定論的な機能設計を実現する。コンポーネントとしては、人工リポソームを利用し、これに B01 班の開発するDNA 分子情報処理システムと、それにより駆動される分子モータ群を実装し、微小管合成による仮足伸長などの機能を実現する。
〇計画研究D01 スライム班「構造化ゲルと化学反応場の協働による運動創発」
分子ロボットの「スケールの拡大」を目的として、ゲル反応場で構成されるスライム型分子ロボットを開発する。そのため、精密に分子設計された高分子ゲルを反応場として、リオーダの非均質な反応空間を生成し、反応生成物の時空間的分布の中でさまざまな分子デバイス群を動作させるための基盤要素技術を開発する。これにより、異方性を必要とする機能、すなわち環境中の濃度勾配をセンシングしてその方向に移動する「走性」のような機能のプログラムを実現する。
早稲田大学 次世代ロボット研究機構
私たちロボット研究者すべてが共通に持つ永遠のテーマは、「人間とロボットの共生」です。『人間の“こころ”はロボットや機械に存在するのか』、『どこまで生きていることに迫れるか』など“究極のロボット”を追求することで、人間を解明しようとしています。次世代ロボット研究機構では、こうしたテーマを追求したいと願っております。
現在の早稲田ロボット研究の特徴は、産業用ロボットに特化せず、“ 人間”という分からないものを対象とし、必ず自分たちでオリジナルのロボットを作ることにあります。私たちは、モノづくりを通して、コンピュータや電気回路、機械の材料、設計に関する知識の他に、医学や心理学など他分野の知識も同時に体得します。また、ロボットは必ずチームでつくるため、コミュニケーション力やチーム力が自然と身につくこと、教育カリキュラムや実験環境が揃っていること、“ 失敗体験”を大切にすること、によって良いロボットづくりができるのも特徴です。次世代ロボット研究機構では、ヘルスケアロボティクス研究所、ヒューマン・ロボット共創研究所、災害対応ロボティクス研究所の3研究所を設置していますが、各研究所間が連携しながら、こうしたロボットづくりを推進していきます。
今後、ロボット研究は、2つの道で未来の社会に貢献していくでしょう。ひとつはロボットそのものが役に立つこと、もうひとつはロボット研究から生まれた新しい先端のモノづくりの技術「RT(Robot Technology)」があらゆるところに応用され役に立つことです。私たちは世の中がどんどんRT化し、大学の研究が社会に還元できるよう実用化を進めています。しかし世の中の人が人間と機械の共生に興味を持たないのでは意味がありません。私たちが分かりやすい言葉で世の中に発信する努力をすることで、大学の研究が世界の平和と人類の幸福を実現させるのだと思います。そのために早稲田のロボット技術を一般公開しています。「RT(Robot Technology)フロンティア」では、人間支援ロボットの研究活動拠点として、定期的に人間支援ロボット体験公開イベントを開催しています。一般の方に体験を通してロボット技術を理解していただくことが目的ですが、若手の研究者を育てることにも役立つと思っています。ロボット研究がさまざまな分野に応用され、さらに未来へ進展するため、私たちは、次世代ロボット研究機構で研究を続けていきます。そして未来の社会に貢献できることを願っております。
超高齢社会の到来を迎えたわが国と先進諸国では、医療・福祉や生活支援などサービス分野へロボット技術(Robot Technology; RT)を導入した新しい産業の誕生が期待されています。今後わが国が世界に先駆けてロボット技術を社会の様々な課題に適用し「真の知的社会基盤」へ成長させるためには、国際的な視野を持つ若手研究者群の育成と、これまで諸工学の集積として扱われてきたロボット技術分野に新たな「体系的学理」を整備することが急務となっています。本拠点の事業推進担当者らは、機械系、情報系、材料系を包含する横断的な研究体制の下に、40年近くにわたって幅広く多様な実績を挙げてきました。
早稲田大学では、ロボット技術の発展を世界に先駆けて「真の知的社会基盤」へ成長させるため、「21世紀COEプログラム」「グローバルCOEプログラム」などを契機に、世界最高水準の「人とロボット技術の共生」を目指した教育研究拠点を設立しました。2008年に始動以降、若手人材育成のための「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」、「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」、国際的人材交流のための「世界最大規模国際サマースクール」、博士学生の体系的教育を目指した「博士課程専修科目の設置」、体系的なロボット学のウェブテキスト「RTPedia」の発行、社会からのフィードバックを直接入手できる交流の場「RTフロンティア」などの特徴的プログラムを通じて、多数の「突破力」のある若手人材の創出と、世界最高水準のRT教育研究拠点を形成してきました。
これらの研究推進力を活かし国際的競争力を更に強化するため、世界のロボット研究中心拠点「次世代ロボット研究機構」を設立しています。上記の新体制を基に、①「高い学問知の構築」、②「学問知を生かした迅速なRTの社会還元」、③実践的アイデアの創造力を併せ持った“突破力”のある若手研究者を多数育成」を実施し、世界のWASEDAとしてより一層尽力して参ります。
次世代ロボット研究機構 機構長 山川 宏
serBOTinQ(サーボットインク)
首都大学東京では、サービスロボットに関する研究成果を社会還元する 仕組みとして、「serBOTinQ(サーボットインク)」という インキュベーションハブを創設しました。名前にあるように サーボット=サービスロボットに特化し、社会の中でどのようなニーズがあり、 地域や家庭内でどんなことがロボットにできるのか? また、大学内や企業のもつ技術を組み合わせながら、 どのようなサービスロボットが考えられるのかを、 実際に販売を前提とした製品開発として提案することによって、 来たるべきロボット社会のために必要な人材育成を含めたプロトタイプを創ります。
山形大学 次世代ロボットデザインセンター
少子高齢化が進むなか,安全で安心して暮らしていける社会を実現するためにロボットテクノロジー(RT)に対する期待が高まっています.また,ロボットテクノロジーを学びたいという学生の要望も強くなってきています.山形大学でも10名以上の教員が,活発にロボットテクノロジーに関連する研究・教育を行っています.そこで,本学理工学研究科では機械システム工学専攻を中心に次世代ロボットデザインセンターを立ち上げました.本センターは,未来ロボットをデザインし革新的な次世代ロボットテクノロジーを創出するための研究・開発の拠点となることを目指しています.また,次世代を担うロボット系エンジニアの育成のために,先端ロボットテクノロジーに関する教育を支援していきます.
京都市立洛陽工業高等学校
【事業概要】
公立工業高等学校
【教育目標】
生徒が、いまのグローバル化した先行き不透明な厳しい時代において、生き生きと活動ができ、他者から信頼される人物へと成長できるように、さまざまな教育活動を展開し、生徒に基礎的、基本的な知識・技能を定着させるとともに、「社会から求められる力」を獲得させる。
また、今年度が、唐橋校舎での最終年度の教育活動になることを踏まえ、生徒が伝統ある洛陽工業高校の一員であることに誇りと責任を持てるような取り組みを展開する。
加賀ロボレーブ国際大会組織委員会
国が「ロボット新戦略」を打ち出したように、加賀市においても、市が打ち出す「加賀市産業振興行動計画」において、「ロボット研究の推進」を最重点項目として掲げ、地場産業の強靭化を目指している。
そのロボット研究の推進を図るため、産業界、教育機関等との連携の下、子どもたちが共同でコンピュータを利用し、ロボット動作のプログラミングを学習したり、操作を体験したりすることで、科学とものづくりのへの興味・関心を高めるとともに、コミュニケーション力、創造力や柔軟な思考力を育む大会である、アメリカ発祥のロボレーブの国際大会を加賀市にて開催する。
国立大学法人 大阪大学
身振り手振り、表情、視線、触れ合いなど、人間のように多様な情報伝達手段を用いて対話できる、社会性を持つ自律型ロボットの実現を目標に、共生ヒューマンロボットインタラクション(人間とロボットの相互作用)の研究開発を推進。
ロボット・トライアスロン運営委員会
「ロボット・トライアスロン」は、3種競技を連続して行う、北海道内の大学生を対象としたオリジナル・ルールのロボット・コンテストです。ロボット・トライアスロン運営委員会は、コンテストの企画・運営を行っています。
生活支援ロボットビジネス研究会(公益財団法人 京都産業21)
(公財)京都産業21では、ライフサイエンス推進プロジェクトの一環として、「生活を豊かにするロボットビジネス研究会」を設立し、会員を募集しています。
ロボットは制御・知能・センシング・ICT・駆動など関連技術の急速な革新に伴い、災害、救助、産業、医療、介護、日常生活などさまざまな分野で本格的な実用化が始まっています。とりわけ、生活を豊かにする生活支援型は、新たな成長産業として急速な市場拡大が期待されています。
本研究会では、京都大学の松野文俊教授を総合アドバイザーに迎え、生活支援ロボットに関心を持つ企業や大学等のメンバーが集まり、国内外のロボット技術や製品・サービスなどの開発動向や市場、今後の成長分野等を調査・情報提供することで府内企業のビジネスチャンスを探ります。
※本事業は、京都府が厚生労働省の採択を受けて、京都市をはじめとする「オール京都」体制のもとで推進する「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト」の一環として実施するものです。
北九州ロボットフォーラム
【北九州ロボットフォーラム設立趣意書】
日本のロボット産業は、自動車産業や半導体産業などを中心としたあらゆる製造業分野に普及、発展してきました。今では世界で使われているロボットの大半が日本で生産され、世界一の「ロボット大国」と言われるまでになっています。現在、産業用はもとより、警備や清掃、介護など身近なところで活躍する次世代ロボットに対する潜在的ニーズが高まりつつあるとともに、ロボット技術をさらに高度化させることで様々な分野への応用が期待されています。2010年には、約3兆円にまで市場規模が拡大する見込みであり、これまで実験的な要素の強かったロボット産業が、実際のビジネスと結びつく時代が近づいているといえます。
北九州市には、世界的な産業ロボットメーカーや、ロボット分野に応用可能な要素技術をもつ中小企業、さらに全国的にも先駆的なロボットベンチャー企業の存在やロボット関連技術の研究開発に取り組む大学、研究機関が集積しています。また、福岡県、福岡市とともに設立した「ロボット産業振興会議」を中心に、「ロボット開発・実証実験特区」の認定を受け、公道上でのロボット歩行実証実験を開始するなど、全国的にも先進的な取り組みを行っています。
長年にわたる「モノづくり」の中で培われてきた技術、人材、そして熱意に加え、これらのポテンシャルを十分に引き出すことにより、北九州市は我が国のロボット産業をリードするロボット産業集積地として大きく発展する可能性をもっているのです。そのためには、産業界、大学、行政が一体となって、これまでのロボットの研究開発にとどまらず実証化・事業化をめざした取り組みを強化し、ロボット産業の拠点化を図ることが必要であり、ここに「北九州ロボットフォーラム」を設立するものです。
つきましては、「ロボット都市・北九州」として、今後、本市が発展するため、皆様のご賛同をいただきますようお願い申し上げます。
平成18年2月
設立発起人
北九州市長 末吉 興一
財団法人北九州産業学術推進機構理事長 阿南 惟正
あいちロボット産業クラスター推進協議会
愛知県のモノづくり産業は、時代の変遷に応じて、業態や主力製品を変化させながら、高度な発展を遂げております。
ロボット産業においても、本県の高いポテンシャルを踏まえ、「自動車」、「航空宇宙」に次ぐ、第3の柱として大きく育てていくことを目指し、平成26年11月に「あいちロボット産業クラスター推進協議会」を立ち上げ、活動を行っております。
産学行政が連携して、ロボットの研究開発や生産の拠点を形成し、新技術・新製品を創出していくことにより、世界に誇れるロボット産業拠点の形成を目指しています。
さがみはらロボットビジネス協議会
国の特区「さがみロボット産業特区」の対象地域として指定された相模原市では、中小企業のロボット技術の高度化や導入促進、また新規事業化など、ロボットをテーマとしたビジネスの推進を多面的に支援するために「さがみはらロボットビジネス協議会」を設立した。
中小企業、大学等研究機関、金融機関、行政や支援機関で構成し、ロボットビジネス推進のための地域のプラットフォームとして、これからの成長分野であるロボット産業の振興や中小企業のビジネス支援に取り組んでいる。
ロボティック普及促進センター
この法人は、一般市民、大学、企業、自治体など広く社会に対して、企業や研究機関、自治体などと連携して、ロボット関連技術の普及促進に関する事業を行い、経済活動の活性化及び、安全安心で暮らしやすい社会の実現に寄与することを目的とする。
ロボティクス研究センター(立命館大学)
立命館大学では、ロボットに関した最新技術の研究を過去20年以上に渡って行なっています。ロボットの研究は産業界、社会の各分野の方々と交流することによって、研究レベルを一層引き上げることが可能です。
当センターでは、共同研究や受託研究などの産官学連携研究のほか、特定研究プロジェクト、公的プロジェクトの申請支援活動を行っています。また、学会などの研究情報の配信や国際的に著名な内外の研究者の講演会、海外の企業・研究機関との研究交流、企業との個別相談等、柔軟且つ迅速な対応で産官学連携を推進しております。
次世代ロボットデザインセンター
山形大学では、10名以上の教員が、活発にロボットテクノロジーに関連する研究・教育を行っています。
そこで、本学理工学研究科では、機械システム工学専攻を中心に次世代ロボットデザインセンターを立ち上げました。本センターは、未来ロボットをデザインし革新的な次世代ロボットテクノロジーを創出するための研究・開発の拠点となることを目指しています。
また、次世代を担うロボット系エンジニアの育成のために、先端ロボットテクノロジーに関する教育を支援していきます。
ロボット産業振興会議
新たなロボット産業の創出を目指し、研究開発の推進、国内外への情報発信、産業化の検討及びロボットに関する理解増進を図る中核的組織として、産学官による「ロボット産業振興会議」を設立することといたしました。
さらに、本会議を中心とした連携の下、全国に先駆けて北九州市及び福岡市にロボット特区を設け、ロボット開発・実証実験を行って参ることとしています。
産業界、大学をはじめとする学術研究機関、そしてロボットに関心をもたれた方々が連携し、一体となって、世界をリードする新たなロボット産業を創出していくことは、地域経済はもちろんのこと、我が国の産業の国際競争力を高めていくためにもきわめて有意義なことであると考えております。