情報ロボット関連組織・団体・企業
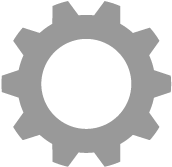
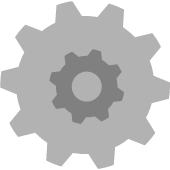
概要
私たちロボット研究者すべてが共通に持つ永遠のテーマは、「人間とロボットの共生」です。『人間の“こころ”はロボットや機械に存在するのか』、『どこまで生きていることに迫れるか』など“究極のロボット”を追求することで、人間を解明しようとしています。次世代ロボット研究機構では、こうしたテーマを追求したいと願っております。
現在の早稲田ロボット研究の特徴は、産業用ロボットに特化せず、“ 人間”という分からないものを対象とし、必ず自分たちでオリジナルのロボットを作ることにあります。私たちは、モノづくりを通して、コンピュータや電気回路、機械の材料、設計に関する知識の他に、医学や心理学など他分野の知識も同時に体得します。また、ロボットは必ずチームでつくるため、コミュニケーション力やチーム力が自然と身につくこと、教育カリキュラムや実験環境が揃っていること、“ 失敗体験”を大切にすること、によって良いロボットづくりができるのも特徴です。次世代ロボット研究機構では、ヘルスケアロボティクス研究所、ヒューマン・ロボット共創研究所、災害対応ロボティクス研究所の3研究所を設置していますが、各研究所間が連携しながら、こうしたロボットづくりを推進していきます。
今後、ロボット研究は、2つの道で未来の社会に貢献していくでしょう。ひとつはロボットそのものが役に立つこと、もうひとつはロボット研究から生まれた新しい先端のモノづくりの技術「RT(Robot Technology)」があらゆるところに応用され役に立つことです。私たちは世の中がどんどんRT化し、大学の研究が社会に還元できるよう実用化を進めています。しかし世の中の人が人間と機械の共生に興味を持たないのでは意味がありません。私たちが分かりやすい言葉で世の中に発信する努力をすることで、大学の研究が世界の平和と人類の幸福を実現させるのだと思います。そのために早稲田のロボット技術を一般公開しています。「RT(Robot Technology)フロンティア」では、人間支援ロボットの研究活動拠点として、定期的に人間支援ロボット体験公開イベントを開催しています。一般の方に体験を通してロボット技術を理解していただくことが目的ですが、若手の研究者を育てることにも役立つと思っています。ロボット研究がさまざまな分野に応用され、さらに未来へ進展するため、私たちは、次世代ロボット研究機構で研究を続けていきます。そして未来の社会に貢献できることを願っております。
超高齢社会の到来を迎えたわが国と先進諸国では、医療・福祉や生活支援などサービス分野へロボット技術(Robot Technology; RT)を導入した新しい産業の誕生が期待されています。今後わが国が世界に先駆けてロボット技術を社会の様々な課題に適用し「真の知的社会基盤」へ成長させるためには、国際的な視野を持つ若手研究者群の育成と、これまで諸工学の集積として扱われてきたロボット技術分野に新たな「体系的学理」を整備することが急務となっています。本拠点の事業推進担当者らは、機械系、情報系、材料系を包含する横断的な研究体制の下に、40年近くにわたって幅広く多様な実績を挙げてきました。
早稲田大学では、ロボット技術の発展を世界に先駆けて「真の知的社会基盤」へ成長させるため、「21世紀COEプログラム」「グローバルCOEプログラム」などを契機に、世界最高水準の「人とロボット技術の共生」を目指した教育研究拠点を設立しました。2008年に始動以降、若手人材育成のための「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」、「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」、国際的人材交流のための「世界最大規模国際サマースクール」、博士学生の体系的教育を目指した「博士課程専修科目の設置」、体系的なロボット学のウェブテキスト「RTPedia」の発行、社会からのフィードバックを直接入手できる交流の場「RTフロンティア」などの特徴的プログラムを通じて、多数の「突破力」のある若手人材の創出と、世界最高水準のRT教育研究拠点を形成してきました。
これらの研究推進力を活かし国際的競争力を更に強化するため、世界のロボット研究中心拠点「次世代ロボット研究機構」を設立しています。上記の新体制を基に、①「高い学問知の構築」、②「学問知を生かした迅速なRTの社会還元」、③実践的アイデアの創造力を併せ持った“突破力”のある若手研究者を多数育成」を実施し、世界のWASEDAとしてより一層尽力して参ります。
次世代ロボット研究機構 機構長 山川 宏
現在の早稲田ロボット研究の特徴は、産業用ロボットに特化せず、“ 人間”という分からないものを対象とし、必ず自分たちでオリジナルのロボットを作ることにあります。私たちは、モノづくりを通して、コンピュータや電気回路、機械の材料、設計に関する知識の他に、医学や心理学など他分野の知識も同時に体得します。また、ロボットは必ずチームでつくるため、コミュニケーション力やチーム力が自然と身につくこと、教育カリキュラムや実験環境が揃っていること、“ 失敗体験”を大切にすること、によって良いロボットづくりができるのも特徴です。次世代ロボット研究機構では、ヘルスケアロボティクス研究所、ヒューマン・ロボット共創研究所、災害対応ロボティクス研究所の3研究所を設置していますが、各研究所間が連携しながら、こうしたロボットづくりを推進していきます。
今後、ロボット研究は、2つの道で未来の社会に貢献していくでしょう。ひとつはロボットそのものが役に立つこと、もうひとつはロボット研究から生まれた新しい先端のモノづくりの技術「RT(Robot Technology)」があらゆるところに応用され役に立つことです。私たちは世の中がどんどんRT化し、大学の研究が社会に還元できるよう実用化を進めています。しかし世の中の人が人間と機械の共生に興味を持たないのでは意味がありません。私たちが分かりやすい言葉で世の中に発信する努力をすることで、大学の研究が世界の平和と人類の幸福を実現させるのだと思います。そのために早稲田のロボット技術を一般公開しています。「RT(Robot Technology)フロンティア」では、人間支援ロボットの研究活動拠点として、定期的に人間支援ロボット体験公開イベントを開催しています。一般の方に体験を通してロボット技術を理解していただくことが目的ですが、若手の研究者を育てることにも役立つと思っています。ロボット研究がさまざまな分野に応用され、さらに未来へ進展するため、私たちは、次世代ロボット研究機構で研究を続けていきます。そして未来の社会に貢献できることを願っております。
超高齢社会の到来を迎えたわが国と先進諸国では、医療・福祉や生活支援などサービス分野へロボット技術(Robot Technology; RT)を導入した新しい産業の誕生が期待されています。今後わが国が世界に先駆けてロボット技術を社会の様々な課題に適用し「真の知的社会基盤」へ成長させるためには、国際的な視野を持つ若手研究者群の育成と、これまで諸工学の集積として扱われてきたロボット技術分野に新たな「体系的学理」を整備することが急務となっています。本拠点の事業推進担当者らは、機械系、情報系、材料系を包含する横断的な研究体制の下に、40年近くにわたって幅広く多様な実績を挙げてきました。
早稲田大学では、ロボット技術の発展を世界に先駆けて「真の知的社会基盤」へ成長させるため、「21世紀COEプログラム」「グローバルCOEプログラム」などを契機に、世界最高水準の「人とロボット技術の共生」を目指した教育研究拠点を設立しました。2008年に始動以降、若手人材育成のための「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」、「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」、国際的人材交流のための「世界最大規模国際サマースクール」、博士学生の体系的教育を目指した「博士課程専修科目の設置」、体系的なロボット学のウェブテキスト「RTPedia」の発行、社会からのフィードバックを直接入手できる交流の場「RTフロンティア」などの特徴的プログラムを通じて、多数の「突破力」のある若手人材の創出と、世界最高水準のRT教育研究拠点を形成してきました。
これらの研究推進力を活かし国際的競争力を更に強化するため、世界のロボット研究中心拠点「次世代ロボット研究機構」を設立しています。上記の新体制を基に、①「高い学問知の構築」、②「学問知を生かした迅速なRTの社会還元」、③実践的アイデアの創造力を併せ持った“突破力”のある若手研究者を多数育成」を実施し、世界のWASEDAとしてより一層尽力して参ります。
次世代ロボット研究機構 機構長 山川 宏
WebサイトURL
所在地
| 住所 |
|---|

