情報ロボット関連組織・団体・企業
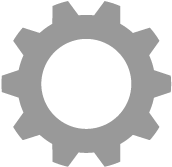
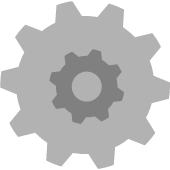
概要
【研究テーマ】
超高齢社会の到来を見据えたアクティヴ・エイジングを支える先端理工学とスポーツ科学の融合研究
【研究概要】
本重点領域「超高齢社会におけるパラダイムシフト」の研究においては、スポーツ科学、ロボット工学、生命科学の3研究グループのこれまでの研究成果を踏まえて、超高齢社会の到来を見据えた先端理工学とスポーツ科学の融合研究を発展させる。「高齢化が進んだとしても、人間として健康で楽しく生活する機能が保持される」社会の構築が不可欠であり、それを支える研究は喫緊の重要課題であるとの認識に至り、“アクティヴ・エイジングを支える先端理工学とスポーツ科学の融合研究”を提案することとした。
Sグループが中心となる研究では、早稲田大学校友を対象としたプロジェクト“WASEDA’s Health Study”を立ち上げ推進する。中高年男女の健康・体力に及ぼすライフスタイルの影響を遺伝子多型、若年期、成人期におけるスポーツ経験と、現在の健康リスク、体力指標(心肺体力、筋力など)と関連させ横断的に明らかにする。また、Rグループと連携して新規運動機器を開発し、それを用いて高齢者に対する健康効果を評価する。さらに、Tグループによって開発された測定系を人に応用した研究へと発展させる。
Rグループが中心となる研究では、ロボット工学、生命科学、スポーツ科学のこれまでの知見を統合し、「アクティヴ・シニアのためのセルフメディケーション」を支援するための基礎理論の確立とそれを支援する機器の開発を一貫して実施する。具体的には、ロボット技術を用いたトレーニング機器開発、スポーツ科学に基づいた高齢者のためのトレーニング開発、 食や生活習慣の健康・トレーニングへの影響の科学的な解明を実施する。
Tグループが中心となる研究では、Rグループと共同で機能性蛍光プローブや導電性高分子を用いたナノシートを開発し、生体情報をモニターするシステムを構築する。また、機能性ナノシートの評価試験はTWInsではin vitro, in vivoまでを行い、Sグループと共同して人を対象とした研究にて実証する。また、時間軸の健康科学や生活習慣病・がん予防の生命科学による基礎的、応用的研究から高齢者の健康効果を実証する。
超高齢社会の到来を見据えたアクティヴ・エイジングを支える先端理工学とスポーツ科学の融合研究
【研究概要】
本重点領域「超高齢社会におけるパラダイムシフト」の研究においては、スポーツ科学、ロボット工学、生命科学の3研究グループのこれまでの研究成果を踏まえて、超高齢社会の到来を見据えた先端理工学とスポーツ科学の融合研究を発展させる。「高齢化が進んだとしても、人間として健康で楽しく生活する機能が保持される」社会の構築が不可欠であり、それを支える研究は喫緊の重要課題であるとの認識に至り、“アクティヴ・エイジングを支える先端理工学とスポーツ科学の融合研究”を提案することとした。
Sグループが中心となる研究では、早稲田大学校友を対象としたプロジェクト“WASEDA’s Health Study”を立ち上げ推進する。中高年男女の健康・体力に及ぼすライフスタイルの影響を遺伝子多型、若年期、成人期におけるスポーツ経験と、現在の健康リスク、体力指標(心肺体力、筋力など)と関連させ横断的に明らかにする。また、Rグループと連携して新規運動機器を開発し、それを用いて高齢者に対する健康効果を評価する。さらに、Tグループによって開発された測定系を人に応用した研究へと発展させる。
Rグループが中心となる研究では、ロボット工学、生命科学、スポーツ科学のこれまでの知見を統合し、「アクティヴ・シニアのためのセルフメディケーション」を支援するための基礎理論の確立とそれを支援する機器の開発を一貫して実施する。具体的には、ロボット技術を用いたトレーニング機器開発、スポーツ科学に基づいた高齢者のためのトレーニング開発、 食や生活習慣の健康・トレーニングへの影響の科学的な解明を実施する。
Tグループが中心となる研究では、Rグループと共同で機能性蛍光プローブや導電性高分子を用いたナノシートを開発し、生体情報をモニターするシステムを構築する。また、機能性ナノシートの評価試験はTWInsではin vitro, in vivoまでを行い、Sグループと共同して人を対象とした研究にて実証する。また、時間軸の健康科学や生活習慣病・がん予防の生命科学による基礎的、応用的研究から高齢者の健康効果を実証する。
所在地
| 住所 |
|---|

