情報ロボット関連組織・団体・企業
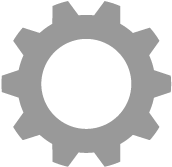
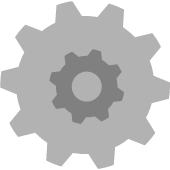
概要
◆領域の概要◆
従来のものづくりの方法論は、すべて材料となる物質の塊を外部から与えた情報に従って加工することで望みの形状を得るトップダウンのアプローチによっている。最近、これとは全く逆の方法論、つまり、物質を構成する分子そのものの性質をプログラムすることにより、その物質自身が望みのものに「なる」ボトムアップのアプローチが注目を集めている。分子そのものを設計し、分子の自己集合によって、原子分解能をもつ人工物を作り上げるこの方法論の出現は、ものづくりの歴史的転換点となることは間違いない。これにより、あらゆる人工物が分子レベルの精度を持つようになれば、生体機能を人工的に再構成できるだけでなく、分子レベルの自己修復、自己改変といったことが可能となり、医療、食料、エネルギーをはじめ、さまざまな分野への波及効果は計り知れないものとなるだろう。技術立国のほか生き残るすべのない我が国としては、今まさに起こりつつあるこのパラダイムシフトを先取りしていくことが必要不可欠であり、そのための新しい学術領域の確立、またそのための人材育成が急務となっている。
本学術領域は、個別の材料やデバイスを「いかにシステムとして組み上げるか」に重点を置いて、人工的な分子システムを構築する方法論の創成を目指す新しい学術領域である。我が国の化学は世界的に見ても極めて高い水準にあり、分子システムのハードウェアとしては、すでに利用可能な要素技術が数多く存在している。しかし化学者だけでは、これらをシステムとして組み上げ、ネットワークとして機能させるためのソフトウェアの開発は困難である。そこで、ロボット工学の方法論を導入してこれらをシステム化し、従来の方法論では達成しえない「プログラム可能な人工分子システム」の実現をねらうのが本学術領域である。人工分子システムの構築は、学術的に極めて重要な研究対象であると同時に、医療、環境、食糧等、我々が直面している諸問題を解決するためのキーテクノロジーになりうるものである。
〇計画研究A01 感覚班「拡散ナノ構造を活用した多元分子情報変換デバイスの創成」
分子ロボットに「感覚」を持たせるため、一分子レベルでの「検出」、「増幅」、「変換」機能をもつ分子デバイスを開発する。DNA オリガミや RNA ナノ構造を用いることで、一定のノイズ存在下でセンシング対象となる複数の分子を多元的に検出し、B01 知能班の開発する情報処理システムへの入力情報を提供する。また、C01 アメーバ班の開発するモデル分子ロボットを対象として、リポソーム膜面上へのセンシングデバイス埋め込み技術を開発するとともに、分子モータ群やゲルアクチュエータを駆動するため、十分な濃度で任意の核酸配列を出力する技術を開発する。
〇計画研究B01 知能班「知能分子ロボット実現に向けた化学反応回路の設計と構築」
分子ロボットの「知能中枢」となる、核酸反応をベースとした情報処理システムを構築する。そのため、高速かつ安定に動作する基本演算素子を開発するとともに、過去の状態を記憶するメモリー素子と、現在の入力情報と記憶に基づいて次の状態を決定する計算機構(状態遷移機械)を実現する。
〇計画研究C01 アメーバ班「アメーバ型分子ロボット実現のための要素技術開発とその統合」
単分子型分子ロボットの限界を乗り越えるため、サブミクロンサイズのコンポーネントを人工的に合成し、その中に情報処理や運動のための分子デバイス群を統合することで、反応速度論に基づく決定論的な機能設計を実現する。コンポーネントとしては、人工リポソームを利用し、これに B01 班の開発するDNA 分子情報処理システムと、それにより駆動される分子モータ群を実装し、微小管合成による仮足伸長などの機能を実現する。
〇計画研究D01 スライム班「構造化ゲルと化学反応場の協働による運動創発」
分子ロボットの「スケールの拡大」を目的として、ゲル反応場で構成されるスライム型分子ロボットを開発する。そのため、精密に分子設計された高分子ゲルを反応場として、リオーダの非均質な反応空間を生成し、反応生成物の時空間的分布の中でさまざまな分子デバイス群を動作させるための基盤要素技術を開発する。これにより、異方性を必要とする機能、すなわち環境中の濃度勾配をセンシングしてその方向に移動する「走性」のような機能のプログラムを実現する。
従来のものづくりの方法論は、すべて材料となる物質の塊を外部から与えた情報に従って加工することで望みの形状を得るトップダウンのアプローチによっている。最近、これとは全く逆の方法論、つまり、物質を構成する分子そのものの性質をプログラムすることにより、その物質自身が望みのものに「なる」ボトムアップのアプローチが注目を集めている。分子そのものを設計し、分子の自己集合によって、原子分解能をもつ人工物を作り上げるこの方法論の出現は、ものづくりの歴史的転換点となることは間違いない。これにより、あらゆる人工物が分子レベルの精度を持つようになれば、生体機能を人工的に再構成できるだけでなく、分子レベルの自己修復、自己改変といったことが可能となり、医療、食料、エネルギーをはじめ、さまざまな分野への波及効果は計り知れないものとなるだろう。技術立国のほか生き残るすべのない我が国としては、今まさに起こりつつあるこのパラダイムシフトを先取りしていくことが必要不可欠であり、そのための新しい学術領域の確立、またそのための人材育成が急務となっている。
本学術領域は、個別の材料やデバイスを「いかにシステムとして組み上げるか」に重点を置いて、人工的な分子システムを構築する方法論の創成を目指す新しい学術領域である。我が国の化学は世界的に見ても極めて高い水準にあり、分子システムのハードウェアとしては、すでに利用可能な要素技術が数多く存在している。しかし化学者だけでは、これらをシステムとして組み上げ、ネットワークとして機能させるためのソフトウェアの開発は困難である。そこで、ロボット工学の方法論を導入してこれらをシステム化し、従来の方法論では達成しえない「プログラム可能な人工分子システム」の実現をねらうのが本学術領域である。人工分子システムの構築は、学術的に極めて重要な研究対象であると同時に、医療、環境、食糧等、我々が直面している諸問題を解決するためのキーテクノロジーになりうるものである。
〇計画研究A01 感覚班「拡散ナノ構造を活用した多元分子情報変換デバイスの創成」
分子ロボットに「感覚」を持たせるため、一分子レベルでの「検出」、「増幅」、「変換」機能をもつ分子デバイスを開発する。DNA オリガミや RNA ナノ構造を用いることで、一定のノイズ存在下でセンシング対象となる複数の分子を多元的に検出し、B01 知能班の開発する情報処理システムへの入力情報を提供する。また、C01 アメーバ班の開発するモデル分子ロボットを対象として、リポソーム膜面上へのセンシングデバイス埋め込み技術を開発するとともに、分子モータ群やゲルアクチュエータを駆動するため、十分な濃度で任意の核酸配列を出力する技術を開発する。
〇計画研究B01 知能班「知能分子ロボット実現に向けた化学反応回路の設計と構築」
分子ロボットの「知能中枢」となる、核酸反応をベースとした情報処理システムを構築する。そのため、高速かつ安定に動作する基本演算素子を開発するとともに、過去の状態を記憶するメモリー素子と、現在の入力情報と記憶に基づいて次の状態を決定する計算機構(状態遷移機械)を実現する。
〇計画研究C01 アメーバ班「アメーバ型分子ロボット実現のための要素技術開発とその統合」
単分子型分子ロボットの限界を乗り越えるため、サブミクロンサイズのコンポーネントを人工的に合成し、その中に情報処理や運動のための分子デバイス群を統合することで、反応速度論に基づく決定論的な機能設計を実現する。コンポーネントとしては、人工リポソームを利用し、これに B01 班の開発するDNA 分子情報処理システムと、それにより駆動される分子モータ群を実装し、微小管合成による仮足伸長などの機能を実現する。
〇計画研究D01 スライム班「構造化ゲルと化学反応場の協働による運動創発」
分子ロボットの「スケールの拡大」を目的として、ゲル反応場で構成されるスライム型分子ロボットを開発する。そのため、精密に分子設計された高分子ゲルを反応場として、リオーダの非均質な反応空間を生成し、反応生成物の時空間的分布の中でさまざまな分子デバイス群を動作させるための基盤要素技術を開発する。これにより、異方性を必要とする機能、すなわち環境中の濃度勾配をセンシングしてその方向に移動する「走性」のような機能のプログラムを実現する。
WebサイトURL
所在地
| 住所 | 〒108-0023 東京都 港区 芝浦3-3-6田町CIC-505 東京工業大学 情報理工学院 小長谷明彦研究室 |
|---|

