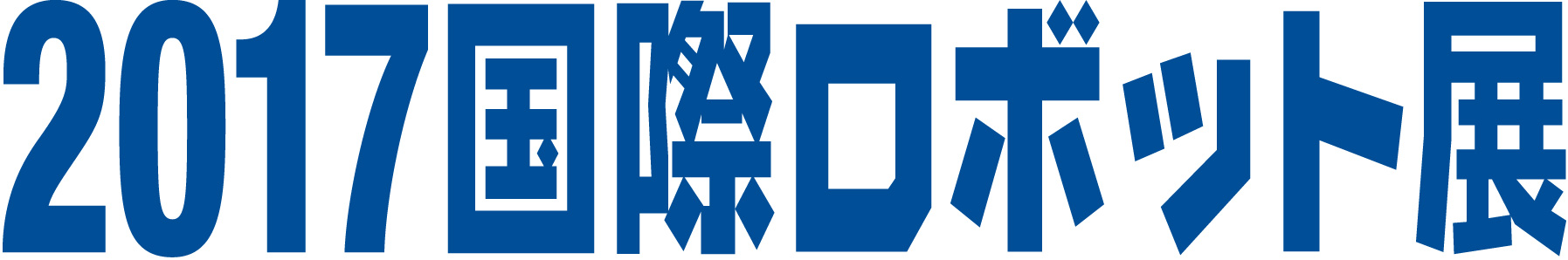KEBA Japanは、2011年にオーストリアのKEBA AGが設立した日本法人です。インダストリアルオートメーションの分野に特化し、主に産業用ロボットや射出成形機、工作機械などの製造業に向けて、革新的な制御システムを開発・提供しています。
「関東」の検索結果
伊豆大島無人観測ロボットシンポジウム 2016(第8回)
〇目的と意義
伊豆大島三原山では先の噴火から30年が経過し、次の噴火について考え・準備しておく必要のある時期になっています。1986年の噴火では爆発的な噴火が発生し、また、カルデラ底や更にはカルデラの外など、思いもかけない地点での活動になりました。そのため、噴火地点には近寄ることができず、噴火現象の科学的理解や災害軽減のための貴重なデータを調査観測する機会を逸しました。このような状況をもたらした理由の一つとして適切な観測技術の未発達が挙げられます。 従って、次の機会には、貴重なデータを観測する態勢を十分に構築しておく必要があると考えられ、とりわけ遠隔操作、無人、不整地走行などの要素を重視した新しい観測用移動体の開発とそれに基づく機動的な対応が望まれます。このような移動体は特に宇宙研究分野で進展しており、火山分野における技術開発に対しても貴重な経験を与えてくれるはずです。一方、宇宙分野では実際の火山などにおけるフィールド実験の経験が乏しく、火山と宇宙との両分野が協力することによってお互いに格段の進展が図られるはずです。本シンポジウムは、このようなことを念頭において企画されております。噴火まであまり時間が残されていないかも知れない今日、宇宙探査や、地球環境計測など、さまざまな分野から、無人観測車(UGV)や無人観測飛行機(UAV) を開発しているグループが伊豆大島に集まり、火山地形での運用実証試験を行いつつ情報交換することで、次の伊豆大島噴火に間に合うように、火山防災や火山活動観測に本当に役に立つロボットと実質的な運用態勢を短年月で完成させることをめざしています。
〇これまでのシンポジウム
2009年度の第1回シンポジウムは、台風の接近により、充分な実証試験はできませんでしたが、多くのチームにご参加いただき、有意義な情報交換の場となりました。2010年度は、天候の影響を回避できるよう、試験期間を長く取り、コア日程の前後の実証試験日程は、チームそれぞれが自由に設定できるようにしました。また、一般の見学者が裏砂漠で見学するのは困難と判断し、コア日程二日目に伊豆大島温泉ホテル駐車場にデモ大会を設定しました。さらに、アウトリーチ活動として、工業高等専門学校や大学の観測移動体をつくっている学生チームに、火山フィールドで動かす体験をする場を提供しました。第3回、第4回と回を重ねて、実証試験とコア日程講演会を組み合わせるスタイルが定着し、参加台数では世界でも類をみない火山観測ロボット実証試験大会へと 成長しました。第3回までの成果をまとめて、日本惑星科学会の学会誌「遊星人」に2号にわったって特集号を組まさせていただき、多数の論文を発表しました。第4回(2012)では大島町の公民館に、第7回(2015)では大島高校学校祭会場に、ロボットを集め、住民のみなさまにロボットを観たり触ったりしていただくデモ大会を開催しました。第5回以降は、近日おこるかもしれない大島噴火に備えた、より具体的な開発や運用実験を行うシンポジウムを心がけております。
平成28年度 光産業技術シンポジウム
〇テーマ:
「~ 未来の自動車・ロボット・産業機器を支えるフォトニクス ~」
〇概要:
本年度の光産業技術シンポジウムは、「未来の自動車・ロボット・産業機器を支えるフォトニクス」をテーマに、一般財団法人光産業技術振興協会と技術研究組合光電子融合基盤技術研究所の共催で開催いたします。
近年のIoT、AI、ビッグデータなどが急進展する社会において、光技術の発展は、我が国の産業や社会を支える基盤技術として、さらには、自動運転を始めとする自動車、ロボット、産業機器を牽引するイノベーションを生み出すきっかけとして期待されています。本シンポジウムでは、自動運転とセキュリティ、LiDAR技術、ロボットの進化、医療イメージング、自動車フォトニクスのテクノロジーロードマップ、および光エレクトロニクス実装システム技術開発について、各分野のエキスパートにご講演頂き、我が国の光産業と光技術の進むべき方向をご議論いただく場といたします。
ロボット農業シンポジウム(分散錯圃グループ)@つくば
日本農業が抱える労働力不足に対応するため2010年に開始した農林水産省委託プロジェクト研究「低コスト・省力化、軽労化技術等の開発」は今年度が最終年となりました。この間、開発した様々なロボットシステムの速やかな実用化・普及が望まれます。他方、ロボットの普及には技術的な課題にとどまらず、ロボット導入による農業経営面の評価や作業の安全性などの検討も必要です。そこで、ロボット農業のあり方について社会的コンセンサスを形成することを目的として市民公開のシンポジウム(講演会・実演会)を開催します。
第9回科学技術におけるロボット教育シンポジウム
本シンポジウムは、WRO Japanの目的に沿い、特に小中高校生向けに自律型ロボットを使った科学技術教育の実践を行っている指導者、支援者のための情報発信、発表および情報交換、交流の場とし、指導者の増加と指導者の実践力のレベルアップを目指します。主に小中高校の教員、指導者を対象とし、さらに小中高校生および教員を支援する高専、専門学校、大学、科学館、企業、NPO等、また社会教育の一環としての実践企業、団体による活発な活動の広がりを目指します。
つくばチャレンジシンポジウム
平成28年度つくばチャレンジシンポジウムを開催します。2016年11月に開催されたつくばチャレンジにおける,各出場団体による屋外自律走行チャレンジの成果をもちより,関係する様々な技術課題についての,参加者相互の情報交換と技術ディスカッションの場といたします。関係者の皆様,ご興味をお持ちの皆様の参加と熱い議論を歓迎いたします。
第1回ロボット技術教育シンポジウム
2016年12月24日(土)、帝京大学宇都宮キャンパスにおいて、「第1回ロボット技術教育シンポジウム」を開催します。
宇都宮キャンパスでは、2015年よりロボットコンテスト「WRO Japan北関東」を主催し、工学系クラブ「ROBOLABO」が2年連続WRO世界大会に出場するなど、ロボット技術関連の活動が盛んになりつつあります。そのような中で、栃木県内外のロボット技術教育に関心のある方をお招きし、基調講演と実践報告を行います。
デジタルヒューマン・ワークショップ&オープンハウス2017
〇テーマ:
「デジタルヒューマンを組み込もう!— 現場を実験室化する組み込み型デジタルヒューマン —」
〇概要:
産業技術総合研究所「デジタルヒューマン工学研究センター」は,2015年4月「人間情報研究部門 デジタルヒューマン研究グループ (DHRG)」として再出発しました. DHRGとして2回目の開催となる第16回デジタルヒューマン・ワークショップ&オープンハウスでは「デジタルヒューマンを組み込もう!」をテーマにミニ講演会,体験型ワークショップ,そしてオープンハウスを行います. 実験室で得られた質の高いデータに基づくデジタルヒューマンモデル・データベースを製品や環境に組み込むことで,生活現場での心理・感覚・行動の計測を実現し,適切な介入を行うことで生活をエンハンスする,という我々の目標をワークショップのテーマに掲げました.
ミニ講演会と体験型ワークショップでは,デジタルヒューマンモデル・データベースの概要を紹介するとともに,これらとIoTセンサをつなげることで現場での運動計測を実現した事例を紹介します. また,オープンハウスでは,研究者と個別にディスカッションすることで,デジタルヒューマンの最前線をより深く理解していただくことができます. ユーザの心理・感覚・行動を情報として取り扱うための計測技術,そしてそれらを変容させるための介入技術は,情報と生活のインタフェースとなるデジタルヒューマンの要です. ワークショップを通じてこれらの技術を実際に体験していただき,デジタルヒューマンとその応用について議論できることを楽しみにしています.
デジタルヒューマン研究グループ 研究グループ長・多田充徳
デジタルヒューマン・ワークショップ&オープンハウス2016
〇テーマ:
「デジタルヒューマンを体験しよう!」
〇概要:
産業技術総合研究所「デジタルヒューマン工学研究センター」は,2015年4月「人間情報研究部門 デジタルヒューマン研究グループ (DHRG)」として再出発いたしました. 実験室で計測した質の高いデータに基づき人間機能をモデル化するだけでなく,現場で計測したデータをモデルを用いて補間し人間機能データとして蓄積する技術,そしてこのモデルを用いて人間の行動や生活に介入するための技術の研究を推進していきます. DHRGとして最初の開催となる第15回デジタルヒューマン・ワークショップでは「デジタルヒューマンを体験しよう!」をテーマに,体験型のワークショップとオープンハウスを行います. 人間の行動や生活を情報として取り扱うための計測技術,そして人間の行動や生活を変容させるための介入技術は,情報と生活のインタフェースであるデジタルヒューマンの要です. ワークショップとオープンハウスを通じてこれらの技術を実際に体験していただき,デジタルヒューマンモデルやその情報・生活インタフェースとしての応用について議論できることを楽しみにしています.
デジタルヒューマン研究グループ長・多田 充徳
第35回日本ロボット学会学術講演会 RSJ2017
第35回日本ロボット学会学術講演会(RSJ2017)は、2017年9月11日(火)~14日(木)に東洋大学白山キャンパス(東京都文京区)で開催されます。
本講演会では、新たな社会基盤としてのロボット技術から、学術的可能性を探求するロボットサイエンスに至るまで、幅広い分野の講演を募集いたします。
とちぎサイエンスらいおん第5回公開シンポジウム「ロボットと人工知能」
第5回目を迎えるサイエンスらいおん公開シンポジウム。
今回は「ロボットと人工知能」をテーマに、ソフトバンクモバイル首席エヴァンジェリストの中山五輪男氏による基調講演をはじめ、県内で活躍している方々による一般講演、会場を交えてのトークセッションなどを予定しております。
また、ロビーでの各種展示や終了後の意見交換会も予定しております。奮ってご参加ください。
■主催
とちぎサイエンスらいおん・帝京大学
■後援(予定)
栃木県教育委員会、一般社団法人栃木県商工会議所連合会、栃木県商工会議所連合会、栃木県中小企業団体中央会、公益社団法人栃木県経済同友会、一般社団法人栃木県情報サービス産業協会、大学コンソーシアムとちぎ、公益財団法人栃木県産業振興センター、株式会社下野新聞社、株式会社とちぎテレビ、株式会社栃木放送、株式会社エフエム栃木
農業ロボット研究会(埼玉ロボットビジネスコンソーシアム)
地域農業の生産性向上や付加価値の創出など、農業が抱える課題に対し、ロボット・ICT技術の 活用を促進するため、最新の開発動向や取組事例を 紹介して課題や方策を深掘りします。
リハビリ・介護ロボット研究会(埼玉ロボットビジネスコンソーシアム)
介護現場のロボット導入ニーズと課題を深堀し、そのソリューションを導入の意義などについてメーカー側とユーザー側が議論し、相互理解を深める研究会です。
埼玉ロボットビジネスコンソーシアム
埼玉県は、ロボット開発メーカー、要素技術を持つ事業者、ロボットを使ったサービス事業者、ソフトウエア事業者、ロボットユーザー(製造業、介護、農業、物流等)、大学・研究機関、金融機関など、異業種のメンバーが参加するプラットフォーム「埼玉ロボットビジネスコンソーシアム」を立ち上げました。
このプラットフォームにおいて、ビジネス交流会や分野ごとにニーズを深堀りして開発に生かす研究会、マッチング支援などを行うことにより、「社会で役立ち・売れるロボット」づくりを応援し、ロボット産業の振興・集積につなげます。
周波数資源開発シンポジウム2016
国立研究開発法人 情報通信研究機構は、2016年7月15日(金)、一般社団法人電波産業会と共同で「周波数資源開発シンポジウム2016 -2020年に向けた新たな無線システム-」を明治記念館にて開催します。
2020年に向けて無線システムは大きく変わろうとしています。我が国は「新たな付加価値産業の創出」をICT成長戦略に掲げ、第5世代移動通信システム(5G)による新たなサービスやビジネスの創出、IoTの実現のため多種多様な機器の接続、ミリ波やテラヘルツ波といった未開拓の周波数帯の開発・利用、あるいは次期技術試験衛星(ETS-IX)といった新たな無線システムの開発が進められています。これらの新たな無線システムの導入に向けて制度的課題の検討を含め、特に我が国の強みである安心・安全な無線システムを国際競争力のある将来の基幹産業として育てるべく、産学官一体で取り組んでおります。
本シンポジウムでは、2020年に向けた新たな無線システムのうち、5Gシステム、IoTの無線通信技術、ミリ波テラヘルツ波帯の無線システム、新たな衛星通信技術について、産学官の専門家による講演を行います。
ROBOCON IN 信州
ロボコンイン信州は、長野県の工業系高校生によるロボットコンテストです。
平成5年(1993年)信州博にて第1回大会が開催され、今年度で第24回を重ねます。 ここでは、ロボコンイン信州の企画についての広報や連絡をはじめとして、県内の工業高校生の技術交流の様子などを紹介しています。
サンデンまえばしロボコン2016 「縁日の王者は誰だ!?Feat.前橋まつり☆」
自作のロボットを操作してボールを集め、自分のターゲットめがけてボールを発射することで、より多くのターゲットを落とすことを目指します。ターゲットは置かれている高さによって点数が異なり、試合終了時に落ちている自分のターゲットとその個数に応じた点数が自分の得点となります。勝敗はその合計得点によって競います。
International Workshop on A Strategic Initiative of Computing: Systems and Applications (SISA): Integrating HPC, Big Data, AI and Beyond
早稲田大学スーパーグローバル大学創成支援(SGU)ICT・ロボット拠点(リーダ:早稲田大学創造理工学部長 菅野重樹)及び早稲田大学アドバンストマルチコアプロセッサ研究所(研究所長:笠原博徳)は、2017年1月18日と19日に、早稲田大学グリーンコンピューティングシステム研究開発センターにて、米国デラウェア大学Prof. Guang Gaoと早稲田大学 笠原博徳教授(IEEE Computer Society President 2018)をWorkshop Chairとして、第一回International Workshop A Strategic Initiative of Computing: Systems and Applications (SISA)‐‐Integrating HPC, Big Data, AI and Beyond‐‐を開催致します。
このワークショップは、米国政府を中心に検討されているHPC・ビッグデータ・AI技術を統合する戦略的コンピューティング・イニシアティブにおけるシステムとアプリケーション技術を、米国・ヨーロッパ・アジアの技術・政策のリーダ達にお集まり戴き、各テーマ毎の招待講演とパネルディスカッションを通し、今後の各技術の最先端を共有し、今後の統合のあり方について議論することを目的としています。
キーノートスピーカは、世界的に著名な産業界・大学・国立研究所の技術的・政策的リーダで、日本からの招待講演者はHPCとビッグデータの産官学のリーダの皆様、中国からも現在世界最速のスパコンのアーキテクト・国家HPC戦略委員の皆様、インドからはHPCプロジェクトリーダ、ヨーロッパからもHPCとAIのリーダの皆様が最先端の話題を紹介して下さいます。
第3回シンポジウム「Challenges of the Second Year」(早稲田大学 博士課程教育リーディングプログラム 実体情報学博士プログラム)
「早稲田大学 博士課程教育リーディングプログラム 実体情報学博士プログラム」が実質的に始まってから1年半強が経過しました。招待講演や学生の活動報告を含む形でシンポジウムを開催。
サイバニクス国際フォーラム2013
【ご挨拶】
私ども筑波大学最先端サイバニクス研究拠点は、内閣府「最先端研究開発支援プログラム」に採択された「健康長寿社会を支える最先端人支援技術研究プログラム」の拠点として、2010年3月より研究開発を推進しています。この度、2011年のフォーラムに引き続き、2013年3月23日(土)に「サイバニクス国際フォーラム2013」を開催いたします。
2011年3月に開催した「サイバニクス国際フォーラム2011」おいては、2日間で約1000名の参加をいただき、最先端人支援技術及び健康長寿社会の技術的・社会的課題およびその対策等について、講演及びパネルディスカッションを通じて当該研究プログラムを紹介いたしました。その後、臨床試験で使用できるロボットスーツの研究開発を行い、国内外の医療機関にて治験に向けての臨床試験を開始するなど、当該プログラムの成果が着実に出始めています。
「サイバニクス国際フォーラム2013」では、工学・医学医療系の各国の著名な有識者を招聘し、最新の研究状況の報告を行うと共に、パネルディスカッションの場で当該分野の研究成果を着実に社会実装するための課題と対策を明らかにすることにより、当該プロジェクトの研究課題達成を効率的に行ってまいります。
ご興味、ご関心のある方は、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。
【概要】
内閣府 最先端研究開発支援プログラム 最先端サイバニクス研究拠点では、研究交流を推進する機会として山海嘉之 研究統括を中心に、関連分野の著名な研究者、有識者及び広く海外から講演者を招聘し、国際フォーラムを開催します。
超高齢社会へ向け、国内外で注目を集める最先端人支援技術の内容・研究進捗および課題解決に関し、専門家・研究者・医療関係者・企業等へ 情報発信および情報共有するとともに、国内外から当該分野における専門家を招へいし、研究内容等の公開、技術交流することで、本プロジェクトの研究課題達成の実効性や効率性の向上を図ることを目的としています。
【ミッション】
当該最先端研究では、脳神経系から身体系に至る生理生体支援技術/身体機能を拡張・増幅・補助する動作支援技術の研究開発を推進し、身近に最先端人支援技術がある未来の実現を目指します。身体機能に障害のある方や高齢者が自立して安心・安全に生活できる「活力ある健康長寿社会」に向けた未来開拓に挑戦しています。
産業総合研究所 人工知能研究センター 人工知能セミナー
産総研 人工知能研究センターでは、人工知能研究に関する情報交換を目的として、原則として月に一度、外部の方やセンター内研究者を講師とする人工知能セミナーを開催します。多くの方々にご参加いただき活発な議論が行われることを期待しています。
どなたでもご参加いただけますが、登録が必要です。参加費は無料です。
青少年のためのロボフェスタ 2016
企業、団体、学校より、コミュニケーションロボット、医療介護用ロボット、競技用ロボット、宇宙研究用ロボット、教育用ロボットなどいろいろなロボットが大集合します。最新の技術を見て触れて楽しみながら学んでください。なんと操作体験もできるブースもあります。
この青少年のためのロボフェスタは、平成17年度から青少年センターで始まり、平成25年度からは、さがみロボット産業特区と連携して神奈川総合産業高等学校を会場にして開催しています。
会場は様々なロボットでにぎわいます。集まれ!!未来の科学者たち!!
〇日時:平成28年11月19日(土)、20日(日)10:00~15:00
〇会場:神奈川県立神奈川総合産業高等学校
(相模原市南区文京1-11-1)
〇参加費:当日受付 入場無料!
〇同時開催:高校生ロボット競技大会
高校生ロボット競技大会 会議室(11月19日 準備、20日 競技大会)見学ができます。
第24回全国高等学校ロボット競技大会(11月5日・6日、石川県)と同じルールでもう一
度ロボットを改良してチャレンジするという、リトライチャレンジの競技大会です。
競技の内容は、全国大会が開催された石川県の特徴を生かしたものになっています。
競技時間は3分間。リモコン型ロボット「としいえ君」と自立型ロボット「北陸新幹線」が、
石川県の兼六園、大聖寺(だいしょうじ)、小松、羽咋(はくい)、七尾の5エリアから、
小松空港エリアやのと里山海道エリアを通り、石川県の伝統工芸品である「てまり」、
「山中塗(弁当箱)」、「輪島塗(盆と箸箱)」を「金沢城」へ運びます。
得点とタイムで順位が決まります。神奈川県内の工業系の高校生が自ら設計して製作した
ロボットで競技をします。これは白熱の競技になること間違いないです。応援よろしくお願いします!
介護に役立つロボットコーナー(大和市)
高齢化が進むなか、介護をする人、される人双方の負担の軽減や介護予防が大きな課題となっています。
市は、介護に役立つロボットを広く知ってもらうために、文化創造拠点シリウス4階に「介護に役立つロボットコーナー」を開設しました。
一部のロボットは実際に触れることができます。また体験会も実施します。
2017 国際ロボット展
〇開催趣旨:
国内外における産業用・サービス用ロボットおよび関連機器を一堂に集めて展示し、利用技術の向上と市場の開拓に貢献し、ロボットの市場創出と産業技術の振興に寄与する。
〇テーマ:
「ロボット革命がはじまった ―そして人に優しい社会へ」
〇主催:一般社団法人 日本ロボット工業会、日刊工業新聞社
〇会期:2017年(平成29年) 11月29日(水)~12月2日(土)
〇会場:東京ビッグサイト 東 1、2、3、4、5、6 ホール
〇開催時間:10:00~17:00
〇同時開催:
・「2017 部品供給装置展」(主催:日本部品供給装置工業会、日刊工業新聞社)
会期:11月29日(水)~ 12月2日(土)
・「2017 洗浄総合展」(主催:公益社団法人日本洗浄技能開発協会、日本産業洗浄協議会、日刊工業新聞社)
会期:11月29日(水)~ 12月1日(金)
・「SAMPE JAPAN 先端材料技術展 2017」(主催:先端材料技術協会、日刊工業新聞社)
会期:11月29日(水)~ 12月1日(金)
・「モノづくりマッチングJapan 2017」(主催:日刊工業新聞社)
会期:11月29日(水)~ 12月1日(金)