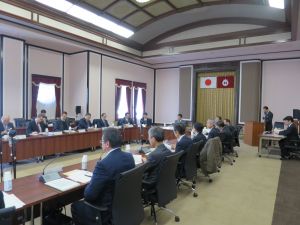平成27年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業における募集要項について、下記公益財団法人テクノエイド協会ホームページに掲載されておりますので、ご案内いたします。
記事一覧
福祉用具・介護ロボット実用化支援事業(高知県)
ロボット関連産業創出モデル事業(徳島県)
徳島県は、国の成長戦略や県の「次世代分野進出支援事業」の実施を踏まえ、本県におけるロボット関連産業の創出を図るため、産学官がコンソーシアムを形成し、潜在的な需要が高い「医療・介護」分野を中心にロボットテクノロジー(RT)を活用した具体的目標の設定や要素技術のブラッシュアップにより、県内企業の参画と徳島発の試作開発・検証を行う。
介護ロボット導入支援事業(香川県)
香川県では、事業者が介護ロボットを導入する経費の一部について助成します。補助額は、購入等にかかる費用の2分の1以内とし、1機器(1計画)につき10万円を上限とします。
介護ロボット導入促進事業(岐阜県)
岐阜県では、介護人材の確保を目的として、介護保険施設等へ広く介護ロボットの普及を促進し、働きやすい職場環境の構築を図るため、国が公表した重点分野に該当する介護ロボットの導入に対し、補助金を交付します。
介護ロボット導入支援事業(群馬県)
介護ロボットの導入に必要な購入またはレンタルに要する経費。ただし、知事が適当と認めた介護ロボットに限る。
介護ロボットは市場化されて間もない状況にあるものが多いため、県では介護現場で有効に活用できるか実証を行います。
介護ロボット導入支援事業(大分県)
県では、平成27年度中に介護ロボットを導入する介護サービス事業者に補助金を交付する「介護ロボット導入支援事業」を実施します。 介護ロボットを導入することは、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備として有効とされています。
介護ロボット等導入支援特別事業(熊本県)
介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資することを目的とする。
医療・介護ロボット未来戦略事業
当財団では、新たに成長が期待できる医療・介護分野への参入を促進するため、医療・介護ロボットの開発を委託し、県内企業間連携や産学官連携を促進させて医工連携による県内産業の振興を図ることを目的に、「医療・介護ロボット未来戦略事業」の募集を開始します。
医療・介護ロボット創造プロジェクト事業補助金(鳥取県)
公益財団法人 鳥取県産業振興機構が、県内の医療・介護機器開発企業と連携して行う医療・介護機器の試作品開発事業に対して助成することにより、県内企業の医療・介護分野への部材供給等の参入技術の取得など、医工連携を推進することを目的として交付する。
介護ロボット等導入支援特別事業費補助金(広島市)
広島市では、国の平成27年度補正予算において「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」が盛り込まれたことに伴い、地域介護・福祉空間整備推進交付金(ソフト交付金)を活用した補助制度の実施を検討しています。
なお、提案内容や国の交付金の配分状況、本市の予算措置状況によっては、協議をいただいても補助金の交付対象に至らないこともありますので、あらかじめ御承知おきください。
生活支援ロボットビジネス研究会(公益財団法人 京都産業21)
(公財)京都産業21では、ライフサイエンス推進プロジェクトの一環として、「生活を豊かにするロボットビジネス研究会」を設立し、会員を募集しています。
ロボットは制御・知能・センシング・ICT・駆動など関連技術の急速な革新に伴い、災害、救助、産業、医療、介護、日常生活などさまざまな分野で本格的な実用化が始まっています。とりわけ、生活を豊かにする生活支援型は、新たな成長産業として急速な市場拡大が期待されています。
本研究会では、京都大学の松野文俊教授を総合アドバイザーに迎え、生活支援ロボットに関心を持つ企業や大学等のメンバーが集まり、国内外のロボット技術や製品・サービスなどの開発動向や市場、今後の成長分野等を調査・情報提供することで府内企業のビジネスチャンスを探ります。
※本事業は、京都府が厚生労働省の採択を受けて、京都市をはじめとする「オール京都」体制のもとで推進する「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト」の一環として実施するものです。
ロボット特区実証実験推進協議会
つくば市は、平成23年3月25日、日本で初めて「モビリティロボット実験特区」として、内閣総理大臣より認定されました。モビリティロボットは、現行法上、日本の公道を走行することができないため、実用化のための実証実験を行うことができません。
つくば市では、つくば市内の一定エリアの公道において、モビリティロボットの社会的な有効性や歩行者等との親和性、社会受容性等についての検証実験を行っていきます。ロボット特区実証実験推進協議会は、人にやさしい次世代ロボット産業の育成にむけて、モビリティロボット実験特区や実環境におけるロボットの実証実験を推進するために設立する協議会です。
豊田市立ち乗り型パーソナルモビリティ実験特区(搭乗型移動支援ロボットの公道走行実証実験)
豊田市が構造改革特別区域法に基づき内閣府に申請した「豊田市立ち乗り型パーソナルモビリティ実験特区(以下「本実験特区」)」が、内閣総理大臣による認定を受けました。 平成26年秋の公道でのウィングレットの走行実証実験に向け、準備を進めます。
パーソナルモビリティロボット「Winglet」の公道走行実証実験
平成28年3月24日
トヨタ自動車株式会社
港湾局
(一社)東京臨海副都心まちづくり協議会
このたび、臨海副都心内の公道(歩道)を使って、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という。)が開発するパーソナルモビリティロボット「Winglet(ウィングレット)」の公道走行実証実験を開始することになりました。
Wingletなどの、いわゆる搭乗型移動支援ロボットの公道走行実証実験は、これまで特区制度の利用により、つくば市や豊田市などで取り組まれてきましたが、平成27年7月にこれが全国展開され、同様の内容・要件にて実施可能になりました。そこで、国内でも先進的なエリアのひとつである臨海副都心において、この実験を新たに実施することとしました。
なお、臨海副都心は、全国展開後に当該措置によって実証実験を行う国内初の地域となります。
今後、トヨタや東京都等による安全確認等の試験走行を経たうえで、平成28年4月下旬から、一般の方々を対象とする乗車体験会を開催していきます。
北九州ロボットフォーラム
【北九州ロボットフォーラム設立趣意書】
日本のロボット産業は、自動車産業や半導体産業などを中心としたあらゆる製造業分野に普及、発展してきました。今では世界で使われているロボットの大半が日本で生産され、世界一の「ロボット大国」と言われるまでになっています。現在、産業用はもとより、警備や清掃、介護など身近なところで活躍する次世代ロボットに対する潜在的ニーズが高まりつつあるとともに、ロボット技術をさらに高度化させることで様々な分野への応用が期待されています。2010年には、約3兆円にまで市場規模が拡大する見込みであり、これまで実験的な要素の強かったロボット産業が、実際のビジネスと結びつく時代が近づいているといえます。
北九州市には、世界的な産業ロボットメーカーや、ロボット分野に応用可能な要素技術をもつ中小企業、さらに全国的にも先駆的なロボットベンチャー企業の存在やロボット関連技術の研究開発に取り組む大学、研究機関が集積しています。また、福岡県、福岡市とともに設立した「ロボット産業振興会議」を中心に、「ロボット開発・実証実験特区」の認定を受け、公道上でのロボット歩行実証実験を開始するなど、全国的にも先進的な取り組みを行っています。
長年にわたる「モノづくり」の中で培われてきた技術、人材、そして熱意に加え、これらのポテンシャルを十分に引き出すことにより、北九州市は我が国のロボット産業をリードするロボット産業集積地として大きく発展する可能性をもっているのです。そのためには、産業界、大学、行政が一体となって、これまでのロボットの研究開発にとどまらず実証化・事業化をめざした取り組みを強化し、ロボット産業の拠点化を図ることが必要であり、ここに「北九州ロボットフォーラム」を設立するものです。
つきましては、「ロボット都市・北九州」として、今後、本市が発展するため、皆様のご賛同をいただきますようお願い申し上げます。
平成18年2月
設立発起人
北九州市長 末吉 興一
財団法人北九州産業学術推進機構理事長 阿南 惟正
地方創生農林水産業ロボット推進協議会
農業と工業の連携は、農林水産業の生産性の改善だけでなく、工業側にも新たなマーケット開拓や新技術獲得の機会を生み出します。また、農工連携により創られる新たな農業技術体系は、世界をリードする新たな武器、未来の“グローカル”ビジネスとなる可能性を秘めています。
私たちは、日本の産官学が有する農業生産技術とロボット技術を融合し、ロボットを活用した農林水産業の新たな形を目指すと共に、各地域産業の活性化、世界をリードする新産業領域の構築を目指しています。
防衛省 技術研究本部 先進技術推進センター
M&S、ロボットシステム、人間工学、CBRN対処などの研究を行っています。また、先進技術を適用した将来装備システムの研究の計画を立案・推進しています。
その中でも、研究管理官(ヒューマン・ロボット融合技術担当)では、装備品等についての人間工学及びロボット技術並びにそれらの連携融合技術についての考案、調査研究及び試験を行っています。
一般社団法人 日本ロボット学会 ヒューマンセントリックロボティクス研究専門委員会
「ヒューマンセントリックロボティクス研究専門委員会」は、社団法人日本ロボット学会において認可、設立された第I種研究専門委員会です。
ロボット外科手術や、福祉・リハビリへのロボット技術の応用、さらには日常生活を支援するサービスロボットの実現など、人間を中心にした次世代ロボット技術に関し、情報交換や共同プロジェクトの立ち上げにより九州地区の研究開発の活性化を図ることを目的とする。
自動車技術会 カー・ロボティクス調査研究委員会
本委員会は、自動車技術会とロボット学会が合同で2008年に立ち上げた調査研究委員会で、提唱している「カー・ロボティクス」は、自動車とロボットを融合さ せ、新しい発展を期待しようという試みをさしている。既にセンサ、ECU、アクチュエータなどの構成が近い両者の技術融合により、移動のさらなる知能化が図られ、また新たなモビリティが発想され、提案されつつある。
そこで、共通的な要素の多い自動車技術やロボット技術における研究者、約30名を委員に迎え、それぞれの分野を超えた横断的な視点による調査研究によって、異分野の研究や研究者の交流促進を図っていくことと共に、カー・ロボティクス分野の確立を目的としている。
一般社団法人 日本ロボット学会 北海道ロボット技術研究専門委員会
北海道における地域ニーズに対応できるロボット技術の創造的発展に資するため、北海道地域のロボット及びメカトロ等関連する学術技術分野の研究者、技術者、経営者、学生が研究発表、討論、交流ができる地域研究拠点を目指す。
ロボット支援手術検討委員会
JSES(日本内視鏡外科学会)が我が国の医療を発展させる原動力となるためには、会員諸氏のさらなる協力が不可欠であります。内視鏡外科がもたらす外科治療のイノベーションは、私たちの絶え間ない努力と新しい発想によって生み出されます。
これからも個々の会員とともに、常に進化する学会を目指していきます。
ロボット哲学研究専門委員会
本委員会では、ロボットと人間の安心できる共存に注目し、安心という言葉の語源となる仏教哲学の考え方や、ロボットとの社会的関係における倫理や規範について議論を行うことを目的とします。特に、ロボットをどのように扱うべきなのかや、ロボットの社会的価値とは何かについて、ロボット工学、哲学、心理学、社会学の立場から、哲学的な視座を創出することを目的とします。
介護ロボット等導入支援特別事業【厚労省】
介護従事者の介護負担の軽減を図る取組が推進されるよう、事業者負担が大きい介護ロボットの導入を特別に支援するため、一定額以上( 20 万円超)の介護ロボットを介護保険施設・事業所へ導入する費用を助成する。
介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル事業【厚労省】
介護ロボットの導入を推進するためには、介護ロボットの開発だけでなく、導入する施設において、使用方法の熟知や、施設全体の介護業務の中で効果的な活用方法を構築する視点が重要。そのため、当事業において、介護ロボットを活用した介護技術の開発までの実現を支援する。
大分県ロボットスーツ関連産業推進協議会
「東九州メディカルバレー構想」の取組の一環として、医療機器産業集積の重層化を図り、拠点化を一層推進するため、平成26年3月に「大分県ロボットスーツ関連産業推進協議会」が設立された。
介護ロボットHALを活用したトレーニング施設「大分ロボケアセンター」の開設を契機に、CYBERDYNE(株)のご協力を得て、県内企業の医療・介護用ロボット関連産業への参入を支援するとともに、ロボケアセンターでのトレーニングと豊富な地域資源を組み合わせた長期滞在型旅行商品を開発し、県内外からの誘客にも取り組む。
あいちサービスロボット実用化支援センター
ロボットの開発側と利用側が開発段階から連携し、新たな技術・製品の創出を促進するため、国立長寿医療研究センター内に「あいちサービスロボット実用化支援センター」を設置しています。
ここでは、医療や介護等のサービスロボットの実用化に向けた開発者側の相談対応や、展示コーナーにおいてサービスロボットの実演展示を行い、利用側である介護施設や医療機関等に、ロボットに関する正しい認識を持っていただく取組などを行っています。
あいちロボット産業クラスター推進協議会
愛知県のモノづくり産業は、時代の変遷に応じて、業態や主力製品を変化させながら、高度な発展を遂げております。
ロボット産業においても、本県の高いポテンシャルを踏まえ、「自動車」、「航空宇宙」に次ぐ、第3の柱として大きく育てていくことを目指し、平成26年11月に「あいちロボット産業クラスター推進協議会」を立ち上げ、活動を行っております。
産学行政が連携して、ロボットの研究開発や生産の拠点を形成し、新技術・新製品を創出していくことにより、世界に誇れるロボット産業拠点の形成を目指しています。
かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会
川崎・神奈川には、高度部材産業や摺り合わせ型産業の集積、全国に先駆けた「かわさきロボット競技大会」による人材やネットワークの蓄積、関連研究機関の立地などロボット関連産業のシーズが高度に集積している。
当協議会では、次の実現に向け、ビジネスモデルの確立、新たな市場の創成、安全に関する社会のコンセンサスづくり、産学・産産連携の推進など、関係者が一致協力して、ロボットビジネスが成功する環境づくりを図っている。