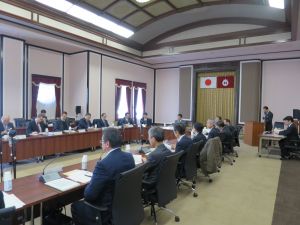本会では、シンギュラリティ(技術的特異点)に関する公開講演会や勉強会を定期的に行い、シンギュラリティを様々な側面から議論することにより、主として専門家と一般市民の意識改革を行うことを目指している。さらには指導層にまで影響力が行使できれば、願っても無いことである。
「ロボット関連組織・団体・企業」の検索結果
生活支援ロボットビジネス研究会(公益財団法人 京都産業21)
(公財)京都産業21では、ライフサイエンス推進プロジェクトの一環として、「生活を豊かにするロボットビジネス研究会」を設立し、会員を募集しています。
ロボットは制御・知能・センシング・ICT・駆動など関連技術の急速な革新に伴い、災害、救助、産業、医療、介護、日常生活などさまざまな分野で本格的な実用化が始まっています。とりわけ、生活を豊かにする生活支援型は、新たな成長産業として急速な市場拡大が期待されています。
本研究会では、京都大学の松野文俊教授を総合アドバイザーに迎え、生活支援ロボットに関心を持つ企業や大学等のメンバーが集まり、国内外のロボット技術や製品・サービスなどの開発動向や市場、今後の成長分野等を調査・情報提供することで府内企業のビジネスチャンスを探ります。
※本事業は、京都府が厚生労働省の採択を受けて、京都市をはじめとする「オール京都」体制のもとで推進する「京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト」の一環として実施するものです。
ロボット特区実証実験推進協議会
つくば市は、平成23年3月25日、日本で初めて「モビリティロボット実験特区」として、内閣総理大臣より認定されました。モビリティロボットは、現行法上、日本の公道を走行することができないため、実用化のための実証実験を行うことができません。
つくば市では、つくば市内の一定エリアの公道において、モビリティロボットの社会的な有効性や歩行者等との親和性、社会受容性等についての検証実験を行っていきます。ロボット特区実証実験推進協議会は、人にやさしい次世代ロボット産業の育成にむけて、モビリティロボット実験特区や実環境におけるロボットの実証実験を推進するために設立する協議会です。
北九州ロボットフォーラム
【北九州ロボットフォーラム設立趣意書】
日本のロボット産業は、自動車産業や半導体産業などを中心としたあらゆる製造業分野に普及、発展してきました。今では世界で使われているロボットの大半が日本で生産され、世界一の「ロボット大国」と言われるまでになっています。現在、産業用はもとより、警備や清掃、介護など身近なところで活躍する次世代ロボットに対する潜在的ニーズが高まりつつあるとともに、ロボット技術をさらに高度化させることで様々な分野への応用が期待されています。2010年には、約3兆円にまで市場規模が拡大する見込みであり、これまで実験的な要素の強かったロボット産業が、実際のビジネスと結びつく時代が近づいているといえます。
北九州市には、世界的な産業ロボットメーカーや、ロボット分野に応用可能な要素技術をもつ中小企業、さらに全国的にも先駆的なロボットベンチャー企業の存在やロボット関連技術の研究開発に取り組む大学、研究機関が集積しています。また、福岡県、福岡市とともに設立した「ロボット産業振興会議」を中心に、「ロボット開発・実証実験特区」の認定を受け、公道上でのロボット歩行実証実験を開始するなど、全国的にも先進的な取り組みを行っています。
長年にわたる「モノづくり」の中で培われてきた技術、人材、そして熱意に加え、これらのポテンシャルを十分に引き出すことにより、北九州市は我が国のロボット産業をリードするロボット産業集積地として大きく発展する可能性をもっているのです。そのためには、産業界、大学、行政が一体となって、これまでのロボットの研究開発にとどまらず実証化・事業化をめざした取り組みを強化し、ロボット産業の拠点化を図ることが必要であり、ここに「北九州ロボットフォーラム」を設立するものです。
つきましては、「ロボット都市・北九州」として、今後、本市が発展するため、皆様のご賛同をいただきますようお願い申し上げます。
平成18年2月
設立発起人
北九州市長 末吉 興一
財団法人北九州産業学術推進機構理事長 阿南 惟正
地方創生農林水産業ロボット推進協議会
農業と工業の連携は、農林水産業の生産性の改善だけでなく、工業側にも新たなマーケット開拓や新技術獲得の機会を生み出します。また、農工連携により創られる新たな農業技術体系は、世界をリードする新たな武器、未来の“グローカル”ビジネスとなる可能性を秘めています。
私たちは、日本の産官学が有する農業生産技術とロボット技術を融合し、ロボットを活用した農林水産業の新たな形を目指すと共に、各地域産業の活性化、世界をリードする新産業領域の構築を目指しています。
大分県ロボットスーツ関連産業推進協議会
「東九州メディカルバレー構想」の取組の一環として、医療機器産業集積の重層化を図り、拠点化を一層推進するため、平成26年3月に「大分県ロボットスーツ関連産業推進協議会」が設立された。
介護ロボットHALを活用したトレーニング施設「大分ロボケアセンター」の開設を契機に、CYBERDYNE(株)のご協力を得て、県内企業の医療・介護用ロボット関連産業への参入を支援するとともに、ロボケアセンターでのトレーニングと豊富な地域資源を組み合わせた長期滞在型旅行商品を開発し、県内外からの誘客にも取り組む。
あいちロボット産業クラスター推進協議会
愛知県のモノづくり産業は、時代の変遷に応じて、業態や主力製品を変化させながら、高度な発展を遂げております。
ロボット産業においても、本県の高いポテンシャルを踏まえ、「自動車」、「航空宇宙」に次ぐ、第3の柱として大きく育てていくことを目指し、平成26年11月に「あいちロボット産業クラスター推進協議会」を立ち上げ、活動を行っております。
産学行政が連携して、ロボットの研究開発や生産の拠点を形成し、新技術・新製品を創出していくことにより、世界に誇れるロボット産業拠点の形成を目指しています。
かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会
川崎・神奈川には、高度部材産業や摺り合わせ型産業の集積、全国に先駆けた「かわさきロボット競技大会」による人材やネットワークの蓄積、関連研究機関の立地などロボット関連産業のシーズが高度に集積している。
当協議会では、次の実現に向け、ビジネスモデルの確立、新たな市場の創成、安全に関する社会のコンセンサスづくり、産学・産産連携の推進など、関係者が一致協力して、ロボットビジネスが成功する環境づくりを図っている。
さがみはらロボットビジネス協議会
国の特区「さがみロボット産業特区」の対象地域として指定された相模原市では、中小企業のロボット技術の高度化や導入促進、また新規事業化など、ロボットをテーマとしたビジネスの推進を多面的に支援するために「さがみはらロボットビジネス協議会」を設立した。
中小企業、大学等研究機関、金融機関、行政や支援機関で構成し、ロボットビジネス推進のための地域のプラットフォームとして、これからの成長分野であるロボット産業の振興や中小企業のビジネス支援に取り組んでいる。
ロボットビジネス推進協議会
ロボットビジネス推進協議会は、経済産業省等との連携・協力のもと、広く産業界、団体、研究機関等からの参加を募り、RT関連ビジネスを振興するにあたって以下の3事業(①RTソリューションビジネスの事業化支援 ②技術開発を含めた中長期的な新産業の創出支援 ③RT政策の提言)を柱に活動を行っています。
(一般社団法人 日本ロボット工業会ウェブサイトより)
なお、 ロボットビジネス推進協議会は、平成28年3月9日開催の平成28年度通常総会において、本年7月31日をもって解散することが機関決定されました。
平成27年2月に「ロボット新戦略」が日本経済再生本部で決定され、同年5月にはその戦略の実現に向けた組織として「ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)」を設立し、活発な活動が推進されています。
このロボット革命イニシアティブ協議会の活動内容は、ロボットビジネス推進協議会が取り組んできた活動の多くを包含しています。従って、それぞれの会員企業にとってその重複に伴う非効率性や負担増を解消するため、ロボットビジネス推進協議会を解散し、重複部分はイニシアティブ協議会にその活動を移管するとともに、重複しない活動についてはロボットビジネス推進協議会を日本ロボット工業会の内部組織として残し、活動継続をすることといたしました。
日本産業用無人航空機協会
日本で運用される産業用無人航空機(UAV)の安全運航を促進し、UAV市場の健全的育成と発展に寄与することを目的として組織された業界団体。
事業内容は、産業用無人航空機の安全かつ健全な利用のため必要な各種基準の策定、認定制度の制定と運営、必要な調査、研究及び技術の向上。各国機関・団体・組織との連絡、調整及び協力。
一般社団法人 日本UAS産業振興協議会
近年飛躍的な発展を遂げている無人航空機システム(UAS:Unmanned Aircraft Systems)の、民生分野における積極的な利活用を推進するとともに、UASの応用技術の研究開発、安全ルールの研究、人材育成、環境整備に努め、UAS関連の新たな産業・市場創造、健全な育成と発展に寄与するために、非営利・中立の立場でさまざまな活動を行います。
ロボットイノベーション研究センター
ロボット技術の適用対象業務の分析や投資効率の算定方法、ロボットの仕様設計を支援するための効果・安全評価プロトコル、運用効果を評価するためのログデータの取得・解析技術を確立し、ロボットによるイノベーションを実現するための研究を実施する。
具体的には、介護における被介護者の自立・介護者の負担軽減および虚弱高齢者の屋内外の移動支援を行えるロボットサービス、人間共存型ロボットによる製造を実現し、これらの産業のイノベーションを起こすことを目標とする。
一般財団法人 製造科学技術センター
ロボットとその運用システムの研究開発を通じて、社会の発展と産業競争力の強化を目的とした調査研究、各種委員会の運営、プロジェクト提案活動の支援等を行っています。
様々なタイプの次世代ロボットに関する委託事業をNEDOを始めとする機関から受託し、平成24~25年度には、NEDO委託事業「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」プロジェクトを受託し、認証制度を中心に考察しました。
後期(H24~H25)は、日本発で日本が先導していくべき生活支援ロボットの安全認証事業の永続的な運営に資すると共に、事業のグローバル展開を可能とする為には、果たして何が求められるかについて、認証制度を中心に考察しました。
生活支援ロボット実用化プロジェクト「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」
後期(H24~H25)は、日本発で日本が先導していくべき生活支援ロボットの安全認証事業の永続的な運営に資すると共に、事業のグローバル展開を可能とする為には、果たして何が求められるかについて、認証制度を中心に考察しました。
ロボティック普及促進センター
この法人は、一般市民、大学、企業、自治体など広く社会に対して、企業や研究機関、自治体などと連携して、ロボット関連技術の普及促進に関する事業を行い、経済活動の活性化及び、安全安心で暮らしやすい社会の実現に寄与することを目的とする。
ロボティクス研究センター(立命館大学)
立命館大学では、ロボットに関した最新技術の研究を過去20年以上に渡って行なっています。ロボットの研究は産業界、社会の各分野の方々と交流することによって、研究レベルを一層引き上げることが可能です。
当センターでは、共同研究や受託研究などの産官学連携研究のほか、特定研究プロジェクト、公的プロジェクトの申請支援活動を行っています。また、学会などの研究情報の配信や国際的に著名な内外の研究者の講演会、海外の企業・研究機関との研究交流、企業との個別相談等、柔軟且つ迅速な対応で産官学連携を推進しております。
さがみはらロボット導入支援センター
さがみはらロボット導入支援センターでは、産業用ロボットの導入支援や技術者の育成を通じて、市内ものづくり企業の「生産性の向上」や「競争力の強化」、「労働力不足の解消」を図ります。
本事業は、地方創生交付金を活用し相模原市からの委託により実施しています。
次世代ロボットデザインセンター
山形大学では、10名以上の教員が、活発にロボットテクノロジーに関連する研究・教育を行っています。
そこで、本学理工学研究科では、機械システム工学専攻を中心に次世代ロボットデザインセンターを立ち上げました。本センターは、未来ロボットをデザインし革新的な次世代ロボットテクノロジーを創出するための研究・開発の拠点となることを目指しています。
また、次世代を担うロボット系エンジニアの育成のために、先端ロボットテクノロジーに関する教育を支援していきます。
ロボット産業振興会議
新たなロボット産業の創出を目指し、研究開発の推進、国内外への情報発信、産業化の検討及びロボットに関する理解増進を図る中核的組織として、産学官による「ロボット産業振興会議」を設立することといたしました。
さらに、本会議を中心とした連携の下、全国に先駆けて北九州市及び福岡市にロボット特区を設け、ロボット開発・実証実験を行って参ることとしています。
産業界、大学をはじめとする学術研究機関、そしてロボットに関心をもたれた方々が連携し、一体となって、世界をリードする新たなロボット産業を創出していくことは、地域経済はもちろんのこと、我が国の産業の国際競争力を高めていくためにもきわめて有意義なことであると考えております。
理研 BSI-トヨタ連携センター
本センターは、脳科学と技術の統合によって生み出される可能性に挑戦し、それを通して未来社会のためのイノベーションを創出することを目指して、理化学研究所とトヨタ自動車が包括的な連携に合意して生まれた研究組織である。
両者はまったく異なる目的と沿革と文化伝統をもつ対照的な組織であり、それぞれまったく異なる形で日本の社会に貢献してきた。この二つの組織が共通の目的のために連携し、それぞれの組織の強みを発揮しつつ力強い協力関係を打ち立て、それを通して新しい研究開発のスタイルを生み出すことができれば、我が国の科学技術にとっても大変意味のあることである。
本センターは第2フェーズに入り、1) ニューロドライビング、2) ニューロリハビリの二つの研究領域に焦点を絞って研究を行う。研究を担うのは下に表示された3つの連携ユニットである。連携ユニットは和光キャンパスと名古屋キャンパスの二つの地区におかれる。各研究ユニットは、専任の研究員と理研脳研およ びトヨタから出向の研究員からなり、両者の緊密な協力関係が保持されるような仕組みとなっている。