情報ロボット関連事業
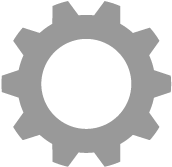
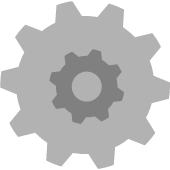
概要
福岡県、北九州市及び福岡市が共同で申請した「ロボット開発・実証実験特区」計画は、平成15年11月28日、構造改革特別区域法による認定を受けました。このことにより、北九州市及び福岡市における公道上でのロボット歩行等実験の途が開けました。
「ロボット開発・実証実験特区」では、規制の特例措置「ロボット公道実験円滑化事業」により、公道でのロボット実証実験を道路使用許可の対象として明確に位置付け、許可手続きを円滑化することで、公道での実証実験実施に道を開きました。
平成16年2月、全国で初めて公道でのロボット実証実験を行って以来、活発に実験を行ってきましたが、その実績が認められ、平成18年1月特例措置「ロボット公道実験円滑化事業」が全国展開されました。
「ロボット開発・実証実験特区」では、規制の特例措置「ロボット公道実験円滑化事業」により、公道でのロボット実証実験を道路使用許可の対象として明確に位置付け、許可手続きを円滑化することで、公道での実証実験実施に道を開きました。
平成16年2月、全国で初めて公道でのロボット実証実験を行って以来、活発に実験を行ってきましたが、その実績が認められ、平成18年1月特例措置「ロボット公道実験円滑化事業」が全国展開されました。
詳細
ロボット特区では、次のような目標の実現を図り、福岡市がロボットに関する研究開発拠点になることを目指しています。
(1)ロボット産業創出に向けた研究開発拠点の形成
人間共存型ロボットの開発に携わる企業や学術研究機関の研究開発実施を支援・促進し、当該特区でのロボットの研究開発実施についてインセンティブを強化すること等を通じて、ロボット研究開発の拠点形成を図ります。
(2)ロボット開発に向けた実証実験の展開
商店街等を始めとした中心市街地の公道空間、市庁舎広場などの市有空間、病院・商業施設などの私有空間などにおいて、適度な人の往来がある環境の下、歩道歩行、段差認知・段差歩行等のロボット実証実験が行えます。ロボット実証実験等で得られた知見は、今後、ロボットを人間の生活領域において活用するうえで、標準規格、安全基準、登録制度、補償制度など必要なルールづくりに役立つと期待されます。
(3)ロボット関連研究者の集積促進
ロボット実証実験を行うにあたっては、ロボット関連企業、大学及び研究機関の研究開発部門で行われているロボット研究の実験フィールドとして特区を活用し、ロボット運用に関する定量評価に必要なデータ集積が行えます。ロボスクエアなどを活用しながら、研究環境の整備を行うこと等により、全国の研究者の集積を促進します。
(4)青少年のロボット科学教育の振興
実証実験の実施により、新しいロボットが市民のみなさまの目に触れることから、これを通じて、市民の科学技術に対する関心の向上、青少年の科学技術教育の振興を行います。公道等での実証実験の見学やロボット操作体験等、特区ならではの科学教育を推進します。
(1)ロボット産業創出に向けた研究開発拠点の形成
人間共存型ロボットの開発に携わる企業や学術研究機関の研究開発実施を支援・促進し、当該特区でのロボットの研究開発実施についてインセンティブを強化すること等を通じて、ロボット研究開発の拠点形成を図ります。
(2)ロボット開発に向けた実証実験の展開
商店街等を始めとした中心市街地の公道空間、市庁舎広場などの市有空間、病院・商業施設などの私有空間などにおいて、適度な人の往来がある環境の下、歩道歩行、段差認知・段差歩行等のロボット実証実験が行えます。ロボット実証実験等で得られた知見は、今後、ロボットを人間の生活領域において活用するうえで、標準規格、安全基準、登録制度、補償制度など必要なルールづくりに役立つと期待されます。
(3)ロボット関連研究者の集積促進
ロボット実証実験を行うにあたっては、ロボット関連企業、大学及び研究機関の研究開発部門で行われているロボット研究の実験フィールドとして特区を活用し、ロボット運用に関する定量評価に必要なデータ集積が行えます。ロボスクエアなどを活用しながら、研究環境の整備を行うこと等により、全国の研究者の集積を促進します。
(4)青少年のロボット科学教育の振興
実証実験の実施により、新しいロボットが市民のみなさまの目に触れることから、これを通じて、市民の科学技術に対する関心の向上、青少年の科学技術教育の振興を行います。公道等での実証実験の見学やロボット操作体験等、特区ならではの科学教育を推進します。
主催団体
福岡県庁
WebサイトURL
お問い合わせ先
| 部署 | 福岡県商工部新産業振興課 |
|---|---|
| 役職 | |
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 092-643-3453 |
| メールアドレス |

